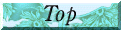現存しない中期英語"The Seven Sages of Rome"の共通種本を全詩行そのまま写本した版はないのかという現代的な幼稚な疑問を抱くのは大学の英作文試験の体験からだ。それは現代小説『一房の葡萄、溺れかけた兄妹 有島武郎』をまず学生達が1センテンスずつ英訳した英作文を板書しそれを教授が添削指導する(「私(教授)の訳文は外人教授(or講師)に確認してもらっていますから...」と言いつつ)講義だったが、前期後期の試験で90,100点 (AA)を獲得した学生の解答はきっと教授が板書した模範英作文の丸写しに違いなかった。
(仏検後に配布される仏作文解答例ではない。)
S.S.例文
C版
4273; Hereefter when þou come on elde
『然も貴郎がその後御老年になられて 金子健二博士訳』
この原文の箇所について E,B, F版は下記のように3版3様であり和訳は
(彼がその年齢になった時、or 年齢を重ねた時,老いた時。)
E版
3522;
Whenne that he to age come,
B版
3654;
When he to his age had come,
F版
2830;
When that he to elde come,
4種類のなかで
「彼が年老いる時」の現代英語訳"When he is (grows,gets) old"
に近似しているのはC版である。C版は、主語you,動詞come, 補語old を用いて S+V+C の形をとる。
when you
come on old
{S=Subject; V=predicate Verb; C=Complement}
他3種の主語はhe,
しかしその文は you を he にして
When he comes on old と単に書き換えたのではなく
主語 he to + age,(his age, old) come {S + V} の語順で動詞 come が使われている。
age (his age, old) comes or come?)
"Spring has come"
『春が来た』のような現代英語から考察するとB版の
he to his age had come においてそれは [his age had come]の部分である。
即ち
E,B,F版はC版を単に写本せずage, his age, old を主語とすることで共通している。
上記のようにまるで作文試験のように同意義異文があるのがローマ七賢物語である。
その発達史を経て英文法が確立していき『中世における物語などの系譜を受け継ぎ、CASIO広辞苑』作者不詳でない15,16,17,18,19,20,21世紀の作家と小説の誕生となったのだろう。
原文各次行
E 3532: And take fro me the Emperice of Rome;
(And take from me the Empress そしてローマ皇后の座を奪う)
B 3655
And have dreven þe owt of Rome
(And have drove the out of Rome
そしてローマから追放した。)
F 2831:
To have takyn for me Emperyce of Rome,
To have taken from me Empress of Rome,
私からローマ皇后の地位を奪うために)
F版の原文forをfromと訳さないと辻褄が合わなくなる。
for だと『私をローマの皇后にするために』となってしまうから。
B版 3656-7:
And vndo all thyn honor /
And haue made hym self emperowre/
(そして陛下のすべての名誉を滅ぼして/自らを皇帝とした。
)
★以下の詩行は17世紀近世哲学の祖
René Descartes ルネ・デカルト 1596-1650 の言葉
フランス語"Je pense, donc je suis"
英語"I think, therefore I am"
『我思う、故に我あり』 の語彙を使って
I think, therefore I am (guilty) と書いてあるような皇后の発言である。
E 3524-5
Therfore hit was alle in my thought
(Therefore it was all in my thought
それ故にすべて私の思考の中にある事だった。)
Hym to dethe ha[u]e jbrougt.
(Him to death have I brought.
王子を死に追いやる)
B 3658-9
Ffor this it was in my thought
(Therefore it was that I'm thinking in my thought
私の心中にある事だったから)
That j wold hym to deth haue browght.
(That I would him to death have brought.)
F 2832-3
And þerfore þus hyt was yn my thoght
Thus to dethe to haue hym broght.
E,B,F版共通の
Therefore it was (all) in my thought について
Therefore ; 故には前の行で述べられている理由の結果として
it was; itは形式上の主語、目的語、
in my thought = I think it in my heart 私は胸中で思う。
次の行で皇后は王子を死に至らしめたかったと自白したのだがそれは動機で殺害したわけではない。
☆ 蛇足だがフランスではデカルト(1596-1650)
の死後異端魔女狩りが衰えてルイ14世(1638-1715)の勅令によってたとえ魔術を行っても犯罪に至らない限り人を死刑にできないことになったと
前頁で引用した。王の机とデカルトの机 & 家臣の机, 市民の机:?
文学史においてThe Seven Sages of Roma はその時代を遡る。
★ 中世英語詩 ローマの七賢物語において
C版の死刑判決は皇妃の妖術魔力に対してであるが、その他のバージョン
E,B,F版では
E:his lords 領主達
B :his tormentor 拷問人
F :barons 貴族達をそれぞれ呼び出すまでの詩行は3種3様
てんでばらばらで最後ページまできて写字生らは独特な語り口となった。
そのどれもが魔術を使ったことを火刑の理由として明記していない。下記参照。
C版 4287-4290『和訳は金子健二博士訳』
Þi witchecraft and þi sorceri
(Your witchcraft and your sorcery
『お前の妖術魔術に対して』)
Sal þou now ful dere aby.
(Shall you now full pay for.
『お前は今非常に高い償いを拂わせられるのだ。』)
Þou grantes þiself here al þe gilt;
(You grant yourself here all the guilt;
『お前は是等の罪悪を自認した。』)
Þarfore es reson þou be spilt.
(Therefore is reason you put to death.
『それ故にお前が死刑に処せられるのは当然な事である。』)
E版 3526-3531
Dame,quothe [the] Emperoure, by synt Martyn,
(Dame, said the Emperor by saint Martyn,
妃よ、皇帝は言った、守護聖人マルタンによりて)
And siche maner dethe shalle be thyn
(And such manner death shall be thine
そしてその死に様は斯く斯くしかじかの如くになるだろう。)
That ordeynste for my chylde,
(That ordain for my child, 『我が子に授けるもの DeepL機械翻訳』)
Þou shalt haue be Mary mylde;
(You shall have be Mary mild,
君は聖母マリアのように柔和であらねばならない。)
And for þou haste opon hym lowen,
(And for you have on him tell lies,
なのにお前は彼に嘘をついていたのだから)
Þou shalt drynke as þou haste browyn,"
(You shall drink as you have death contrive or cause,
貴女は殺害を企んだ犯行動機のように死を飲む(受け入れる)であろう。
)
B版 3660-3669
My lorde,on knees j pray the,
(My lord, on knee I pray you,
閣下、跪きどうか)
This gilt þat thow wilt forgevr me."
(This guilt that you will forgive me.
罪を犯したことを陛下が許してくれるでしょう。 )
"Nay,said þe emperowr, by god almyght,
("Nay, said the emperor , by God Almighty,
否、皇帝は言った、全能の神によりて。)
I shall neuer forgeve the right.
(I shall never forgive the right,
私はお前の真相を許さない。)
All thy knelyng is for nowght;
(All your kneel is for nothing;
お前の跪くポーズはすべて無駄なのだ。)
By hym that me dere hath bowght,
(By him that me dear has bending,
彼によって我が愛しい人が屈服している。
Ryght suche shall be thy jugement
(Right such shall be your jugement
正当にそのような自白があなたの判決となる。)
As thow to hym haddeste ment,
(As you to him had torment
お前が彼に拷問の苦痛を与えたように。)
Thow art beknowen affore vs all.
(You are beknown before us all
貴女は我々の眼前によく知られている。)
Therfor a fowle deth on the shall fall.
(Therefore in an unbecoming or unseemly manner death on you shall fall."
故に妃に不名誉でふさわしくない死が降りかかるであろう。)
F版 2834-2840
Then seyde þe Emperour "withowten lye,
(Then said the Emperour "without lie,
その時皇帝は言った、「偽りなく)
Oon soche a dethe thou schalt dye,
(On such a death you shall dye, そのような死にお前は臨むであろう。)
As my sone schulde haue done,
(As my son should have done,
私の息子を殺害しようとしたように。)
Be gode skylle and ryght reson;
(Be good distinction and right reason;
善悪の弁別と正当な理由で。)
And be þy wordes þat þou aknawe,
(And be your words that you are acknowledge,
そして貴女が自認した貴女の言葉でありなさい。)
Þou art worthy to be to drawe
(You are worthy to be to draw
貴女は刑場に引いて行かれるに足る。)
And to suffur dethe before vu all.
(And to suffer death befor us all.
そして皆の者の面前で死を遂げるのだ。)
★ C,E.B.F,4種各自が特有の上記詩行は、
家来を呼び集める場面で4版それぞれが異なる単語を用いて内容は一致する。
C版 4296-7『金子健二博士訳』
Þe Emperoure gert bifor hym call
(The Emperor prepared before him call
『皇帝は彼れの面前に呼びだしたのは』)
His knightes and hys menge all,
His knights and his mens all,『彼れの武士達や、彼れの凡ての従者達でありました。』
E版 3532
Hys lordys he called to hym euerychon
(His lords he called to him everyone
彼の領主達(貴族達)を皇帝は彼の下に皆呼び寄せた。)
B版 3670
The emperrowr called his tormentowrs
(The emperor called his tormentors
皇帝は彼の拷問者達を呼んだ。)
F版 2841
Anon he dud hys barons calle
(At once he made his barons call
直ちに皇帝は彼の直臣達を呼び集めた。)
上記の使用単語からこの時点で
皇帝が召集したのは例えばフランス革命のギロチンを見届ける公衆ではない。
C版の原文"Sirs "
(複数の称号サー達) を金子健二博士は『皆の者よ..』と和訳したその訳文だけでは原文を誤解する恐れがある。しかしEには、lords
貴族《侯[伯、子、男]爵》...君主、
領主、家長etc.
...everyone と書いてある。
C版は、ローマ七賢物語の典型的登場人物の単語 knight
騎士達、(金子博士訳は武士達),mens
下男、家臣 を用いて
B版は、まずtormentowrs
拷問者達を呼びそして
F版 のbarons には
男爵という訳が耳に馴染みやすいけれども中世期の baron
は近世期以降の小説的ではなかろうか?
The Seven Sages この各1行は4行揃って読むことに意義がある。
以下参照:
C版
4298-9
And sayd "
Sirs smertly for my sake,
(And said "Sirs quickly for my sake,
『そして申しました。「皆の者よ、私の為に、』)
A grete fire þat ge ger make,
(A great fire that you prepare make,
『大きな火を燃やしてくれ、皆の者で」』)
★★★ 火刑場面
E版 3534-3539
Lordelyngys, he sayde, j commaunde you,
Lording, he said I command you,
諸公、彼は言った。「私はあなた方に命じる。
A grete fyre that ye lete make nowe
(A great fire that you let make now
大きな火を今あなた方が起こしてくれ)
To brenne there yn thys womman soo felle
(To burn there in this woman so cruel
『この残酷な女を火刑に処すために DeepL 日本語翻訳』)
For certes, she hathe hyt deseruyd welle,
(For certainly, she has it deserved well,
確かに彼女は当然の報いを受ける。)
Sythe she ordaynyd syche treson,
(Time she oedained such treason ,
彼女がそのような反逆を定めた時間)
To sle my sone agayne reson"
(To kill my son again reason."
私の息子を何度も殺害しようとした理由。)