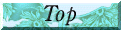王子の第15物語は後世の英文学のような
王位につく予言の末路ではなく海中に投じられた子は高貴な心の持ち主だったので
王と家臣達は、彼らが有する威厳をもって両親に黄金と領地を与えて幸福にした。
☆ F版は without end で王子の第15物語に結末をつけている。
The seven sages of rome (ローマの七賢物語)の中期英語表現は、
rich (happy) end ではなく rich (happy) without end である。
F 2813
He made them ryche withowten ende.
(He made them rich without end.
彼は彼等を限りなく金持ちにした。)
★ 第15物語(予言)を語り終えた王子は
彼の父ローマ皇帝に
大海の波に投げ込まれた子供以上に罪のない私を何故殺そうとするのかと言った。
E版3488;
Thus me thynkythe, fadyr, by goddys tre.
(Thus me thinks , father, by god's tree.
神の木によって私は思う。)
この god's tree は前頁の
F版:For to be hanged on a tee
(木に吊るされるために)のtreeではない。
guilt, guilty の5版5様
E版 3490:
And also lytylle gylte haue j
(And also little guilt I have
罪悪感もほとんどない。)
B版 3603:
No more gilty j than he
(No more guilty I than he
私は彼ほどの罪深い人間ではない。)
F版 2819:
Ageste ryght, withowten gylte
( guess, expect right, without guilt
正道と思う、無罪である)
D版 3377:
And certys I haue no more gylte
(And certainly I have no more guilt
そして確かに私はもう罪を犯したとは思わない。)
C版は guilt, guilty を用いず
trespass (《古風》罪を犯す、法、おきてに背く)で
I trispast na mare þan did he,
I trespass no more than did he,
『私はあの子供以上に罪を犯したことはありませぬ。金子健二博士訳』
★以下は額縁物語においてローマ皇帝の継嗣が語る詩行を
脚韻語に従った和訳。
E版 3505-
中世の邸宅、婦人の私室にて
横たわるよう命じた彼女の by 傍に
私がそうしないので certaynly(certainly) 確かに
彼女は彼女の衣服を裂いた bydene (at the same time )同時に
その理由は wene (suppose) 何だろう
That j hadde hyr inforsyd (outrage?)soo
私は持った彼女の強姦の痕跡?を 速やかに
But certeys er j hadde soo doo
しかし確かにあるいはそうありうる ちぎった
むしろ私の死の方がよい thole 苦しむ、耐え忍ぶ,我慢するよりも
そしてすべて燃やされて cole (coal) 木炭、石炭になった方が
B版 3624-3643
私の真実は貴方の lady 夫人
彼女は私が彼女の横になることを望んだ by 傍らに
しかし私はどうしても fulfill 添えなかったので
彼女の願望と邪悪な will 意図
彼女自身で彼女がすべてをバラバラに引き裂いた ywis (cerainly)確かに
そして私がしたこととして赤裸々にする this これを
すべては彼女が自分に加えた彼女の owtrage (outrage) 暴行を
私を除外するために私の herytage (heritage) 世襲財産から
罪を犯していない私が (I should have been) slayn (killed)
殺されたはずだった。
これは法律違反であった。 sertayn (certain) 確かに
むしろ私は死ぬほどあの世に行きたい gon (gone) 帰らずに
その行為を...くらいなら don (done) 行う
神(星占い)は予言しそれで貴方の lady 夫人
私は彼女に決してさせたことがない vylany (villainy) 悪役を
しかし彼女は私に魔法をかけていた soo (so)そのように死ぬ
私が一言(one word)でも話せば twoo (two) 二言
すなわちこの日が come (become) そうなるように
私の命よりも彼女がなった nome 生け捕りに
彼女自身を貴殿がなさる spye 観察する
私はここに言葉もありません lye (lie) うそ
F版 2822-
そして真実それは私の lady 貴婦人
私を横たわらせたかったので by 傍らに
しかしむしろ私は苦しむ方がいい。 dedd (dead,death) 死を
2825:
Than to have done aftur hur vylous redd
(Than to have done in order to that ,to do her villanious rid,
escape deliver
《単語のみ訳》事を終えるよりも、 するために、 する手段として、悪辣な、いやな、 ひどく不快な行為、 追い払う、 一掃する、 逃れる、 望まれていることをかなえる。)
B版は、E,F版と比較すると
皇后は魔女(witch)或いは魔法使いと相談し王子は7日が過ぎるまでの一語二語を以て死ぬという魔法をかけていたと
詳述して
(上記原文 3638行:But she me had bewyched soo,
bewyched は bewitche (魔法をかけて...する))
王子は...するくらいなら死を苦しみたいと
どんな手段によって何のために死んでしまうのかと葛藤している。
★ 皇帝は皇后に行った。一声で息子の言葉は本当だろうかと。
E版 3516: Ye sys, she sayde,jwys.
(Yes sir, she said, certainly. はい陛下、彼女は言った、承知しました。)
B版 3645: Ye sire, he said, by all men.
(Yes sir, he said, by all men はい陛下、彼は言った、すべての人に。)
F版 2827: Yes syr, withowten othe
(Yes sir, without oath はい陛下、宣誓なしで)
3種類の原文でE,F版は彼女が返答するが
B版は彼(王子)が言ったので
The Emperowr sent for þe emperres
(皇帝は皇后を(玉座に)呼び寄せた。)
☆ サウサーンバージョン(Southern version)の結末は
ミッドランドバージョン(Midland version)の死刑判決で命を落とした以下原文空白と
異なり火刑のシーンの詩行があり
ミッドランドバージョン特有のnigrimancye(降霊術、魔術、オカルトアート)と比較しても
所謂中世の魔女裁判的要素があるのかもしれない。
その様な最終章の行間において
B版写字生は、B 3640:
Or that this day had be com (この日が来る前に)
という1行を入れて
ローマ七賢物語の全枠組み物語に共通する
the morrow 翌日、明日、の意の詩語の残影(残映)的効果を最後まで維持している。
☆ knowledged について
E 3518:
Forcerteys,sir, done your lykynge:
(For certain,sir, done your liking ,
確かにサー貴方の好きなようにしてよいのです。)
B
3547 :
And chargid her to tell how it was.
(そしてどうだったのかを話すよう彼女を非難した。)
B
3548:
She
knowleged in all thynge
(She knew in all things 彼女はあらゆることに精通していた。 )
knowledged という語彙はB版特有である.
knowingと訳せば インテリジェンス (intelligence)利口で如才ない登場人物としてのみ強調されてしまうが
このknowledged は皇后に
火刑になる末路が目前に迫ってもなおその判決に臨んで
七賢人達と対等な品格を備わせているようだ。
しかしB版のknowleged(現代英語 knowledge は名詞である。)はacknowledged (認める)であることが
E,F版ではなくD版との比較(Jill博士の用語解)によって明確になる。
D版 3418-3420
Thus the thef the Emperesse
(Thus the criminal the Empress このように犯人の皇后は)
Knowleched hyre wykkednese
(Acknowledged her wickedness
邪悪の念を認めた。 )
Thorow the fyndys entysment
(Through the Devil's allurement
サタンの誘惑に負けるように黒魔術を用いたことを,
or 悪霊の力によって王子を操るように)
するとB版原文対句
3548-3549
She knowleged in allthynge
Þ:at she wold fayn his son to deth brynge,
は、ファインな息子を死に追いやりたいがために犯したすべてに
魔術を使ったと認めた。
★ ★ ★ ★
The Seven Sages of the Rome ローマの七賢物語
の書かれた中世を知る一助になる本は、
白水社、文庫クセジュ、『異端審問』 (ギー・テスタス/ジャン・テスタス著
安斎和夫訳)です。
特にその第4章 二 悪魔の働き (デモノマニア)75-81ページ
『「悪魔」ディアブルは、・・・13世紀・・・協会は、キリスト信者の世界から
降神術者ネクロマンと魔女ソルシェールを排除しようとしたのである。・・・・魔女狩りの勢いが衰えるのは、フランスでは
1682年以降である。ルイ14世の勅令によって、たとえ魔術を行なっても、それが普通法の犯罪を伴わない限り、その者を死刑にすることはできないことになったのである。・・・・
パリのクレーヴ広場【現在も市役所の前にある】
においてラ・ヴォアザンが焼かれたのは、その二年前であった。』
注※によれば彼女は産婆、占い師、モンパルナス夫人は、
ルイ14世の寵をうけるため、彼女に黒ミサをしてもらった。etc.』
この哲学・心理学・宗教分野の著作を一読すれば
中世ロマンス物語、教訓物語
"The Seven Sages of Rome”
を再び読み解くのは
老いの悲しみではなく面白いと思う。
それは
necromancer:降霊術者、(s.s原文 nigremancie,nigrimancye,nigrimancie:
ケンブリッジ大学ジル博士の用語解:sorcery,通例悪霊のたすけによる魔法、妖術、witchcraft,通例悪事を引き起こす魔法、魔術、妖術を使うこと black magic, 黒魔術 occult art オカルト術、秘学 ,);
C版:A wiche (witch; 魔女)という語彙があるからであるがs.s.ローマの七賢物語の15枠物語には
"Virgil"以外は魔法使いなど登場しないのでそれほど面白くもなくずば抜けて価値がある文学作品だと言い難く満足がない。それでも各バージョンを比較しながら原文一字一字に婉曲的、暗喩的に神や天使や悪魔が存在しているかもしれないと発見に意欲的でも留学せずして日本に暮らし勉強する中期英語詩ローマの七賢物語の探求ははっきり言って無意味。しかしこの無意味を無意味のまま遠い異国の中世文学博士から著作物使用許可をいただきホームページを作成したことに生き甲斐も感ずる。
研究者によれば中英語の韻律物語は原文のまま味わうしかないという。
脚韻が時としてその規則を破りながらも
整然と連なる詩行の内容は卒論を書いた若い日には文学的趣向に引き込まれるように愉快で難解な綴り字を
読み進めていけたものだった。それが時を経ると熟読は苦痛になった。端的に言えば
各枠組み物語の登場人物への感情移入が生ずるとそこに一貫するのは愛と悲嘆、
生きる楽しさ、喜び、幸せよりも人の世の虚しさ、金と欲故の破滅、切なさ、辛さ、惨たらしさそしてあまりにも寂しすぎる故に孤独に読むのが嫌になった。しかし幾多の現存写本バージョン比較による写字生間の虎の巻想像はミステリーである。そして大方のストーリー内容は故意に行うトリックと過失が根底となって"emotion is expression" (『感情は表現である』)
EETS(Early English Text Society)のおかげで削除しなくてよいホームページのThe Seven Sages of Romeを持って『朝トイレットペーパーに感謝できる。教育原理より引用』人間でありたい。
人間は皆死ぬという教育が欠けていると自著で教育原理を講義した大学教授をはじめとして当時履修した教授達は皆死去して私も老人になった。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ローマ帝国皇后の王子殺害動機はすべてのバージョンに共通する。
その供述の前にB版は他にない構文を挿入している。
B版
3651 :
Wherfor j am now in
dispayre;
(for which I am now in despair
そのために私は絶望している。)
このdispayre は前述のknowleged (knowledged)同様
B版だけが持っていて
それは、現代英語例文
"He was in despair of winning the race
彼はレースに勝つことに絶望している。)
に鑑みると
I am in despair = He was in despair
の表現がs.s.
ローマの七賢物語が書かれた時代に
すでに確立していたことになる。
次行は3種すべて和訳は「私は恐れたから」だが書き方は3様である。
E 3520:For j me drad, sayed she,
(For I me dread, said she)
B 3652:And also sore j drede me,
(And also greatly I dread me, feel dread)
F 2828:And all for that y dradd me
(And all for that I dread me)
C 4271:And sir, I dred me ӡit alswa
(And sir, I dread me it also
『陛下よ、私にかういふ事が同様に心配になったのであります。金子健二博士訳』)
以下は、現存しない共通種本を写本した一端例 (今風ならば英作文虎の巻or授業の黒板写しのテスト?The seven sages の数多の写字生達の時代を経て16世紀シェイクスピアが通ったグラマースクールのようになってゆく一連の道筋?)
E:...dystrye me (destroy me (私を破滅させる),
B:...distroyed the, (destroyed you) (貴方を破滅させる),
F:...dysroyed me and þe (destroyed me and you)(私と貴方を破滅させる)
E 3521: That [h]e shulde dystrye me
(That he should destroyed me 彼は私を破滅させる、亡き者にする。)
B 3653: That he wold haue distroyed the,
(That he would have destroyed you, 彼は貴方を破滅させただろう。)
F 2829: That he schoulde haue dystroyed me and þe
(That he should have destroyed me and you
彼は私と貴方を滅ぼすべきだった。)
would, should と have, 動詞の活用形も微妙
☆C,D版にはこの最終局面に共通語彙 destroy がない。