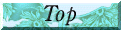王がこれをすべて目撃し聞いた時彼の胸中は幸福感で満たされた。そこで自信をもってその子供を
貴族達の面前に呼び彼の奇知によって多くの知恵を絞ったことを褒め彼は十分な報酬を得た。すなわち
王の第1の契約通りに王はそれをすべての場合において守った。王はその場で娘を彼の嫁にやり
そしてその日のうちに王国の半分を与え
王の治世は過ぎてその死後間もなく彼はとても賢くきれいな人だったので
城を明け渡すことなく国王になり
全ての領主達が彼を愛し始めた。ある日その子供は父と母を思い出した。
このあらましにE版のみ
次の1行がある。
E版 3436:
But as we fynde in gestys jwryte
(But as we find in story (achievement;with effort and skill)
I write
しかし物語(先人の達成,業績)の中で我々が見つけるようにして私が書いている。)
これは写字生達(I,We)がThe Seven Sages の未発見中世期本を写本しながら書いている事を読者に伝えるための挿入句かもしれない。
それはストーリー展開と相まって次行の
3版全てが
彼等は貧困に陥り赤恥を忍んで本国を捨て
彼等の息子の国に逃げそのcityに住んでいたと続く。
|
version(版) |
3版の原文は同じ綴り字 wyste (know)が 主語theyで否定文、
主語child ,king で肯定文
|
| B |
3553:
And they it wyste no thynge.
(And they it know nothing.
彼ら父母は何もそのこと(祖国から移住した国の王が息子だったこと)を知らない。
|
| F |
2750:
That chylde wyste of hys fadurs fare,
(That child know his father's journey,conveyance,equipment,
behaviour,success,fortune,
子供は父の旅、輸送、装備、ふるまい、成功、運命、を知る。)
|
| E |
3443:
And wyste hit in a lytylle tyde,
And know it in a little tide,
そして王になった子供はそれを(彼らの住居)を小潮の時期に知る。
|
ある日その王は、
2人の召使:servant:原文は3版3様の異綴り字
{E版:two seruantys:
B版:two seriantes:
F版 :seryauntes:}
を呼んで王の特殊な任務を帯びて行くように命じた。
原文 F版:2753:
on hys errande goo (on his errand go)
この句は古い用法として現代英語辞書 研究社 新英和大辞典に載っている。
come [go] on an errand of .....
(特殊な使命を帯びて来る、行く・・・)
その特命とは最近母国からこの町に来たばかりの男を探すことだった。
その名前は3版3様である。
E版:3449 Barnarde norysshe sone (バーナード ノーリスの子)/
B版:3563 Gerard noryses sone (ジェラール ノーリスの子)
F版:3759 Jerrard Noryes sone (ジェラール ノーリスの子)/
★そう言えば分かるように(暗号のように?)
Yf以下の王の"台詞"を比較してB,Fが同義であるかについて。
B版: 3564: Yf ye may fynd hym ther
(If you may find him there
もし貴方がそこで彼を見つけることができるなら)
F版: 2761: Yf that hyt were hys wylle,
(If that it were his will,
もしそれが彼の望みであるならば)
の
研究社:新英和大辞典には
will 次のような《古》古い引用文が載っている。
"What is your will? (君の望みは何ですか?)
"It was the king's will that they should die."
(彼らの死ぬことが王の望みだった。)
★しかしThe Seven Sages of Rome:
ローマの七賢物語
を外組として(その内側)王子の第15枠物語(副題:予言)は、この後 happyを扇動的に述べて大団円を迎えるストーリーである。
王の意志は、彼らに部屋を用意させて
F版 2762-4
And sey that the yong kyng
(And say that the young king
そして伝えて下さい。若い王が )
Wyll to morowe withowt lesyng
(Will tomorrow without falsehood
明日虚偽なく欲しています。)
Come and dyne with hym thare
(Come and dine with him there
そこに来て一緒に食事(dinner)をしたいと。
王の台詞は
F 版において子供はThe young king を自称しているが
E,F版においてはI will である。
I wylle to morne dyne.../
j wyll to morow dyne.../
(I will tomorrow dine...)
★
彼等(父母)は
君主を我ら貧しき者のゲストとすることは喜びではなく
悲しいかな王様がお城で簡単に作れる物[F 2980
þe kyng to make at ese; The king to make at easy]を持っていないので
それがかえって我々を不快にするのです
[F 2981 Therfore y am at moche malees;
Therefore I am at much discomfort ]と言った。
しかし王の意志に従ってあるもので
お迎えいたしましょうと王のメッセンジャー達に答えた。
★ come,came (相手の所へ、ある目的地に行く、到着する。)
と go, went(…しに行く)
|
version (版) |
come |
go |
down light 王様が馬から降りる |
| E |
3464:
A morowe the kyng thedyr came
(A morning the king thither came
翌日王はあちらに行った。[hitherならばここへ来た]) |
3467:
Went to mete with hym anon.(Went to meet with them at once.
王とその諸侯達(貴族達)はすぐに彼らに会いに行った。)
|
[...down light の行がない。]
3465:
And with hys fadeyr hys in he name,
(Ans with his father his inn he take.
到着してから彼は父とともに彼の家の戸口までの道をたどる。)
ディナーの戸口までは歩いて行ったと思われる。
|
| B |
3582:
A morowe whan þe kyng come was,
(the morrow when the king was come,
翌日王が到着した時、) |
|
3584-6:
「ようこそあなたの恩寵を」と父が言うと)
Anon as he was down light
(Immediately as he was descand lightly
直ちに彼がすばしこく馬から降りた途端 )
父は彼を家の中に導いた。 |
| F |
|
2784:
On þe morowe þe kyng went to town
(On the morrow the king went to town
翌日王が町へやって来た。) |
2786-8
And at hys Fadurs hows he lyӡt adown,
(And at his Father's house he descended from horse lightly,
そして父の家で彼は軽やかに馬から降りた。)/
彼が知覚した家の中へと父は彼を直ちに正しく導いた。
|
上記E版において
動詞 came の主語は the king ,
動詞 went の主語は He and hys baronys euerychone
(He and his barons everyone 彼と貴族達みんなして行った)
baronsを伴って行った
そのE版には王が軽やかに馬から降りたという文が省略されている。
baron は広義であるが男爵や男爵夫人達よりも貴族達のほうがよいらしい。
さらに《古》(財務裁判所)裁判官
という意味もあるがそれは解釈の範囲ではないだろう。
またbaronは古フランス語派生語であり中世の諸侯という意味もある。
馬から降りたのか馬車から降りたのか
horse ,carriage の語彙がなくとも
中世ロマンス物語では ride, adown,down は馬を御する、降りると訳す。
★食卓につく前に
王になった子供の父が盥を運び置くと王のknyghtes(B版、騎士達)或いはmen
(F版、家来達)が清潔な水を王の手に与え
母はタオルでその手を洗って拭いてあげようとするが...
以下はE,B,F版に共通する描写である。
|
version (版) |
Suffre (Suffer) |
towayle (towel) |
王の御付きの任務
| E |
3473;
But that wolde not suffer the kynge. |
3470-72:
And hys modyr a fayre towayle /
And wolde haue seruyd hym ,sam-fayle /
Fulle mekely at hys waschynge /
(彼の母は汚れのないタオル一枚を持って来た。/
彼に仕えたかった。/
十分に容易に洗えるように。) |
3474-5:
[And] bade a seruande take the towelle thare/
Of the modyr that hym bare. /
(それで王は一人の従者に
母が彼に持って来たタオルを手に取るよう命じた。) |
B |
3591:
But he wolde not in no maneere
Suffre that it so were.
3595:
But he wold not suffre her for no thynge. |
3593-4:
Than cam hid moder /
And browght forthe a ffayre towayll /
To wipe his hondes after hi wasshynge. /
(その時彼の母が来た。そしてタオル一枚を差し伸べた。
洗った後に彼の手を拭くために。)
|
3589:
His knyghtes gaff water to hym,
(王の騎士達が彼に手洗いの水を与えた。)
3596-7:
A knyght of þe kynges that wasse ther /
The towayle to the kynge dide bere
(そこにいた王の1人のナイトがそのタオルを受け持った。) |
| F |
2975:
But that wolde not suffur þe kyng |
2792-94
And hys modur came,withowt fayle, /
And broght a feyre whyte towayle/
To drye hys hondes aftur hys waschyng;
(それから母が来た。/
汚れのない真っ白な一枚のタオルを運んだ。/
洗った後で彼の手を乾かすために。 ) |
2790:
And whyll a men hym watur dud geue,
家来達は王に水を与える間
2791:
Hys Fadur helde hys oon sleue, (父親は水がかからないようにと王の衣の袖を支えた。)
...
2796-7;
But dud hyt take seryaunt there
(しかしそこに控えていた召使がそれを掴み)/
Of hys modur that hym bore.
(母が彼に持ってきたタオルを受け取った。)
|
上記のsufferの文について語彙 suffer 《古文: 許容する、黙って・・・させる?》を用いていないC版は適訳の手がかりを与えないが『彼女は彼女の出来るだけの事をして王様に敬意を表したのだら』
例えば日本のお殿様の苦しゅうないではない。
下記は卒業論文から「子の父は、
'by goddys tre' (by god's tree)神の十字架、絞首台を直ちに考えるキリスト教徒であり
その国の慣習によらなくても旅をしてきた客を盥の水とタオルで疲れを癒すことは
中世期の庶民と騎士達の王に対するもてなしの一つだったように思われるほど原始的な
情景が思い浮かぶ。
B版:But he wolde not in no manere,/
Suffre that it so were.
(But he would not in no custom/
Suffer that it so were.慣習なしには欲しなかった、そうであっても構はず。)
というところに10歳で海に投じられ神の恩寵によって王になった子の沖合の船での予告の瞬間と
礼儀正しく高尚な父母との生活の時との間、代官夫妻との生活、激変した王の職務の時、
これらすべてを線上に繋ぐ行為を読者は強いられる。鳥の鳴く意味を答える者は、
'raven'不吉の兆しを告げる証拠だとallegory(寓意、諷喩)な解釈をした方が面白いだろうか。....」
☆When this washing was all done (この洗浄がすべて終わった時)
下記のC,D版は鴉の船上の予言通りに事が運んだと王が父親に言った。
|
version (版) |
鴉 the ravens , the crakes |
| C |
4218-9:
Fulfild es now þe crakes crying,
(Fulfilled is now the crake's crying;
『今例の鴉の叫びの一件が解決しました。金子健二博士訳』
Þat talde bifore of al þis thing:
(That told before of all thing;
『凡てこの事柄のあることを予め告げていたところの、あの鴉の叫びが 』) |
| D |
3354-5:
Fadyr, nowe hyt hys byfalle
(Father , now it is befallen
父上、今御身に起こっているのは)
That I herde the rauens telle.
(That I heard the ravens told.
私が鴉たちが話すのを聞いた事柄です。)
|
E,B,F版では鴉(raven, crow, crake)の語彙がなく
before this のみで
読者は海の船上での鴉の予言だと分かり切った事としている。そして
3版すべてI を主語とし私が過去に予め貴方に言った未来の出来事が現在の出来事になったのだ。(その出来事は鴉が予言したが省略されている。)
E版:
3476-7
And sayde "fadyr, nowe falle hit ys
(And said "father now fall it is
父上、今貴方の肩にかかっているのは)
that j tallde you sum tyme, jwis
(いつの時か私が貴方に話したことです。確かに。)
B版:
3600-1
"Sire, he said, now ffallen ys,
(Sir, he said now fallen is
サー彼は言った 今行われたのは)
As j to you sayd or this
(As I said to you before this
私が予め告げた通りこの事柄が為されると)
F版:
2800-1
Fadur he seyde, now come hyt ys
(Father he said, now come it is
父上、彼は言った、今その時が来たのです。)
That y to yow seyde before thys
(That I to you said before this
予め私が貴方にこの事(ディナーの洗面器とタオル)について言っておいた事)
☆鴉の予言したthisとは
父よりも富裕層の身分になる事だったが息子は王になっていたのだ。
(しかしカラスは王になるであろうとまで予言しなかった。)
王は海に投じられたが神の恩寵によって
死なずに生きて貴方の前にいると言うと
父親は大いなる悲しみを持って恐怖の念に駆られぎょっとした。
即ち
E.B.Fの3版はすべて絞首刑を恐れた。
E:3485:
Or ellys hangyde or drawe
(Or else hanged or draw
さもなくば絞首刑に処せられるか
すのこそりにのせて あるいは裸馬に乗せ刑場に引いて行かれる)
B:3608:
To be hangid and to drawe
(To be hanged and draw.)
F:2808
For to be hanged on a tree,
(木に吊るされるために。)
C版は単に彼に殺される。(語彙は slw ;slay ,kill )
D版ではその箇所の原文は空白[.......]である。