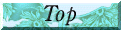城守或いは門番のおかげでcastle内に住まわせてもらっていた子供は王の宮廷(E:3349
the kyngys corte;The king's court)に一緒に行くことになった。
B版ではconstable =him の代名詞を用いずに his master (彼の師)と語彙を変えてある。
F:2644
The chylde prayed hym þen, as he was hende,
(The child prayed him then,as he was gracious,
その時子供は彼に懇願した、彼は親切だったので、)
E:3350
Sum maner goode ther to lere
(Some manner good there to learn
そこで学ぶべき良い方法があると連れだった。
)
貴族達が参殿すると皇帝はどなたか
(E:3355 If any of you)
(B:3466 yf any of you)
(F:2652 ys þer any of)
教えて下さいと言った。
なぜ昼夜私がどこにいても(B:where euer j be :(where ever I am))
私に泣きつくのか。どなたか(whych of you)それを教えてくれたものには
私の娘をその者に嫁がせて
王国の半分の領地(E,F,C,D版)を与えるとも言った。
(B版はすべての所有地)
下記はそれぞれの写本箇所
E:3160
And halfe my londe by my day,
(And half my land by my day, 私の時代の私の領地の半分 )
F:2658
And my kyngdome haluendele
(And my kingdom half territory,or district
私の王国の半分の領地、或いは地域)
B:3473
And all my londe after my lyff
(And all my land after my life
そして私の生涯を終えた後私の凡ての土地を)
C:3991
And half my kingdom ilka dele
(And half my kingdom same portion,
王国の相続分の同じ半分
『領地の半分を悉く割いてやります。金子健二博士訳』
ミッドランドバージョンD:3231
I wyl gyf hym alf my londe
(I will give him half my land
私は私の領地の半分を彼に与えます。)
★サウサーンバージョン B:3491
What this marvel myght be
(この驚異はなんだろう)という王の言葉で
直ちに子供が王と貴族の前に立ち上がると彼が美少年タイプだったので
(B 3495 For he was of hewe bryght)
貴族と騎士達は彼を注視した。
子供は、
E: lordyngys euerychone (lords ,everyone)
B: Lordynges echon
F: Lordynges
3版全て共通 "lord" 皆さんと呼び掛けて
E: see ye the rauyn (see you the raven)
B: Ye se the rauen (You see the raven)
F: Ye see that rauen (You see that raven)
同様にして御覧の通りここに立っている(E)
座っている(B.F)一羽のカラスは雌であり
他の2羽の雄達とこの不和状態が去年もありました。
より大きく黒いカラスは年長者で
朝夕悲しく泣いているメスと30年共に住まっていました。
E:3390 xxx yere....dwellede (dwelled )/
F:2692 xxxij yere ...helde (held)(32年)...愛情を保っていた。/
C: 4049 al threty (thirty) ӡere/
★自然界の事象をカラスにとっての飢饉とする箇所の比較
E:3394-5
For hit was tho a dere yere
(For it was then a dear yere
物価がひどく高い年だったので
)
And scars of vytayle and stouyre
(And rare of vitality and provision, food
体力不足と食料の備えがわずかになった。)
F:2693
Then come a tyme þat corne was dere
(Then come a time that corn was dear,or expensive
商人が穀物を法外に高く売る時代が来ました)
B: 3507
That all thyng was full dere,
(いっさいの物が全く高価になった。)
C:..corn was dere ..『穀物が物価高騰となった。金子健二博士訳』
その時節に年長の黒色カラスは
メスが荷厄介になり彼女を捨てたのです。
E,B.F,C の4版における共通事項は、
forsake (現代英語:forsake. forsook, forsaken, 親しい人、場所などを...もために見捨てる、居たい場所を去る、従来の習慣などを捨てる、)をそれぞれが異なる二つの対句で綴り字を変えて二度用いることである。
下の表にそれらのforsake、forsokeを並べたが行番号はE以外前後している。
この繰り返し語句が写字生達のレタリングの妙ではなく中期英語の文法の変化形だったと推理できる。
|
version (版) |
共通 had forsake |
共通 forsoke |
| E |
3393:
Yonde female alone hadde forsake (Young female alone had forsaken 若い雌は一羽きりで捨てられた。) |
3396:
The grete rauyn the femalle forsoke (The great raven the female forsook
大カラスはメスを捨てた。 )
|
| B |
3510:
Whan he had her forsake (When he had her forsaken
彼が彼女を見捨てた時) |
3508:
Therfor he forsoke her tho
(Therefore he forsook her then
故に彼はその時彼女を見捨てた。) |
| F |
2696:
And when the elder can hur forsake
(And when the elder can her forsake
そして年長者が彼女を見捨てることができる時) |
2694:
And therfore he hur forsoke
(And therefore he her forsook
だから彼が彼女を見捨てた。) |
| C |
4055:
"Þus when þe alder hir gan forsake.
(Thus when the older her began forsake.
『年長者の鴉がこのやうにして彼女を棄てゝ仕舞ったのです。金子健二博士訳』) |
4051
Þarfor þe alder hir forsoke,
(Therefore the older her foesook,
『さういった訳から、この年長者の鴉は彼女を棄てゝ仕舞ったのです。』
|
★スペル共通要素から中期英語:
forsakeの不定詞はforsake/
単純過去形はforsoke/
過去分詞形はforsake/ と推定できるかもしれない。
☆
文法からストーリーに立ち返ると
年上のオスは若い雌をもう連れて行こうとせず
彼女は行こうか行くまいか分からなかったが(オスが何処へ行ったのか知らなかった。)
年長者の雄が雌との巣を放棄することができたその時
若く小さい雄がその雌を交尾のパートナーとして
今日(this day)まで彼女を保護してきた。彼のさえずりは
この国の王である貴方に誓って(he say the,per fay)彼女を手放さないと
言っているのです。
★この写本の箇所でまた特異となるのはD版である。
上記4版には天候の描写がないがD版には簡潔な詩行があるのだ。
D:3271
In a wedyr that was colde,
(In aweather that was cold,
天候は寒かった。)
さらにつがいのメスを追い払って仕舞った理由を
鴉の雄はとても年を取っていたので
彼の(彼女の)食べ物を適正に見つけてやれず
大食らい(gluttony)だったからと明記したのはD版唯一である。
D:3274
For glotonye he brake hys fayth
(Because of gluttony he broke his word
大食いのせいで彼は約束を破った。)
D版においては大食いのために年をとっていたカラスがメスを置いて飛び去ったのではなく
雌を巣から追い出してしまったのだから
その場合 forsake を用いていない。
老いの鴉によって彼らの巣から追い払われた
メスが逃げ回っている時にメスを探している一羽の若いカラスに出会ったのである。
(D版本文の注釈参照)
★ D版特有の語彙
glotonye (gluttony) について
gluttony は、The Seven Deadly Sins (
七つの大罪の1つ:暴食...gluttony /
強欲...greed /
色欲...lust /
憤怒...wrath /
怠惰...sloth /
傲慢...pride /
嫉妬..envy / )
D版だけが用いていた単語
gospel (福音)
については既に前頁に述べてある。
七つの大罪とはキリスト教の西方教会、
カトリック教会における用語でその中期英語の一語glotonyeを引用したからと言って
D版D写字生は他の写字生達よりもキリスト教に精通していたとは思わない。
☆D版には3羽の鴉の生態描写の前後に天気にかかる簡潔な対句がある。
3248-5
The colde wedirs was agoo,
(The cold weather was gone, 寒い天候は去りました。)
Vngyr, colde, and al wo.
(Hunger, cold, and entire woe.
飢え、寒さ、そしてすべての災い。)
このcoldの繰り返しは、D版写字生にとって自然界の過酷さを示唆しているのかもしれない。
(前出はIn a weather that was cold.(3271))
D版においては
老カラスがメスを巣からけり落としたにもかかわらず
活力が回復すると雌を追ってそのメスと若いオスとの巣まで飛んできたのである。
★ E, B, F, C版の写本の読み方はD版と異なり
天候が回復したというような記述なしにある日突然
次のような詩行が現れる。
F:2700
And now ys the elder comyn agayne,
(And now is the older come again,
そして今再び年長の鴉がやって来た。一旦放棄した巣でメスは他の若いカラスとつがいとなって生きのびていた。)
いずれにせよワタリガラス《不吉の兆しとされる》だが彼らの巣の在りかは不問である。
第15物語の主人公の子供は船上で船尾に止まった
鴉の予言の言葉を聞き取れたせいで父によって海に投げられて溺れそうになったところを漁夫に救われ
王の国の城代に売られた。その子供が王様の頭上で夜となく昼となく鳴くカラス達の言葉を告げようとしている。
E,B,F,.C 『何れも或る英吉利の中世期本を種本として書いたものであると言うに
帰着するのである。C版の日本語訳者:金子健二博士の本書の由来から引用文』
下記の表は前表の鳥達の対句や共通語彙"forsake"と同様に
研究者達の推理の根拠となる例文である。
|
version (版) |
共通な shall be |
共通な shall have |
| E |
3401:
Hos make that she shalle be.(Who mate that she shall be.
彼女は誰の妻となるべきか。 |
3404:
Whych of hem hyr shall haue (Which of them her shall have
どちらが彼女を所有するだろうか。) |
| B |
3515:
Who shall her trewe make be (Who shall her true consort be.
誰が彼女の真の相手となるべきか。) |
例外 3519:
Whan they know who shall be þer make.
(When they know who shall be thier mate
彼らは誰が彼らの伴侶になるかを知る時である。 |
| F |
2705:
Whethur make that sche schall be .(Whether consort that she shall be
彼女は二者のいずれの伴侶となるべきか。) |
2709:
Then ye haue demed who schall hur haue,.(Then you have judged who
shall her have. その時あなたは誰が彼女を所有すべきかを判断したことになる。)
|
| C |
4072:
Wheþer make þat sho sal be, (Whether mate that she shall be.
『彼女が二羽の中の何れの妻となるべきかをお定め下さい。金子博士訳』) |
4077
Wheþer of þam þat hir sal haue, (Whether of them that her shall have, 『即ち彼等の中の何れが彼女を妻として所有し得るかを御決定下さるならば。』 |
The Seven Sages of Roma ではここでもまたD版との比較が不可欠がとなる。
D版の第15物語の冒頭は、was (be), hadde (have),を用いて
'There was a man that was bolde
(There was a man that was excellent
一人のずば抜けた男がいた。)
[・・・・・・欠行・・・・]
And hadde a vertu that was hyghe
(And had a virtue that was high
そして気高い美徳を持っていた。(徳が高かった))
virtue という単語はヴァーチュとしか訳せないことに意義があり
何か心地よいこの語感を例えば〇〇字以内で述べるのは至難の業である。 The Seven Sages の詩行においてVirtue は頻出する語彙ではなく all versions
全枠組み物語で最も用いる語は fine である。
表のE,B,F,C版と明らかに異なる筆写(Dの筆致)によって若いカラスの主張から王の判決までを
端的に書き表しているがその部分を抜粋すると。(このホームページ本文参照)
D:3290
He chalanged hire for hys:
(He laid claim to her for his:
『彼は彼女を自分のものだ主張した。DeepL機械翻訳』)
D 3306-7
He schal haue that he ches,
(He shall have that he chose,若いカラスは彼が選んだものを所有する。)
And the holde go makelees.
(And the old go without a mate.
そして年老いた鴉は伴侶なしで行くがよい。)
★E,F,版の要約~
年長の鴉は飢饉の時ひどく薄情だった。
本当のことを言えば彼はつらい目に会わなかったのだから。
もしも飢えがメスの鴉を死に至らしめたならなどという考えは
露ほどにもなかった。
従って今後彼が彼女を娶ることはない。
2羽の老いた方のオス鴉がこの判決の事由を聞いた時直ちに(3版共通行末 anon:immediately)
一叫び上げて裁判を傍聴していた者皆が驚く所から飛び去った。以下の対句は前置詞の使用と内容において
3版3様である。
|
version(版) |
sorrow |
|
| E
| 3422:
And made sorowe, and fly away,
(And made sorrow,and fly away, そして悲しみを飛び立たせたのだ。) |
3423:
That neuyr men of hym say,
(That never men of him say.
それが彼(老いの鴉))の人達が決して言わないことだ。) |
| B
| 3528:
And in gret sorow he flewe away,
(And in great sorrow he fly away,
そして大きな悲しみのうちに彼は飛び去った。) |
3529:
And never after non man hym say,
(And never after no man him say.
そしてその後誰も決して彼をいう事はない。) |
| F
| 2726:
And all with sorowe he flewe away
(And all with sorrow he fly away
そして悲しみとともに彼は飛び去った。) |
2727:
To seke hym a make where that he may;
(To seek him a mate where he may;
一対になる鳥の一羽をどこにでも探し求めるために。) |
もう一方の若いカラスはメスを連れて互いに楽しそうに歌いながら年長の鴉とは別方向に飛んで行ってしまった。