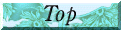前のページの
[E 3220-3223]
[B 3420-3423]
[F 2612-2615]
4行における couplet (2行連句) & couplet (2行連句)について
いわゆる dream a dream のような 同族目的語構文
sing a song の視点から
sing/song を'couplet'の脚韻のようにずらして筆写してしまいそうになるが
詩行の脚韻構成は次のようである。
1.couplet 2.couplet
[E] thynge/synge/ songe/longe
[B] thynge/synge/ songe/longe
[F] thyng/syng/ song/long
rhyme とは?
韻、押韻 詩学:二つ以上の語または末尾で最後の強勢ある母音が等しく
1.y 2.o
それに続く子音が等しい。1.nge or ng 2.nge or ng
かつその前くる子音が異なっている。
1. th/s 2. s/l
よって
E, B, F 版はすべてこの規則通りに写本できている。
末尾の母音字 e の綴り字は
[E,B] eをつける /eをつける
[F] e をつけない/eをつけない
という流儀できっちりそろえてある。
sing / song は、
強勢母音が i/o で異なりその前の子音 s/s が等しい。?
子供に言う鳥たちの言葉はクォーテーションマーク"quotation marks"で書いてあり
上記coupletの2行目の「呼びかけChild,お前はそれほど長くはない。」
とhas heard とwill help を用いるcouplet との3行から成っている。
|
version (版) |
共通 had herad |
共通 will help |
| E
| 3324:
But Jesus Cryst hathe hyrde the bone (But Jesu Christ has heard your request
しかし神イエス・キリストはあなたの頼みを聞いておられる。{for 4 day を補うと
has heard は現在完了用法「継続」でもう4日間ずっと聞いている}) |
3325:
And wolle the heple fulle welle sone
(And will help you full well soon.
そうともそのうちにあなたを完全に助けて下さるだろう。) |
| B |
3424:
For god hath harde childe's boon.
(For god has heard child's prayer という訳は神はあなたの祈願を一度お聞きになったのだから {once を補うと has heard は現在完了用法「経験」で4日前に一度お聞きになったことがある。}) |
3425:
And the he will helpe full sone.
(And he will help you full soon. そして彼は直ぐにあなたを十分に助けて下さるのだ。)
|
| F |
2616:
For god hath harde now þy boone.
(For god has heard now your prayer 神は今やあなたの願いをお聞き入りになられた。
{has heard now は現在完了用法「完了」で願いが叶う時が来た。}) |
2617:
And he wylle helpe þe full soone.
(Amd he will help you full soon.
そして彼はすぐにあなたを十分に助けて下さるのだ。)
|
★ The Present Perfect:
現在完了形を考察するために
F版のnow に従って
E版に時間の長さを表す副詞:for 4 days を補い
B版に:once を補って試訳しました。
☆動詞の時制の視点から前頁に戻ると
子供が海で溺れかけた時
神(イエス)を呼び求めたから神がそれを聞いたの詩行はすべてPast(過去)=Simple Past(単純過去)で書かれている。
[E]:He called to god..(couplet 2行目)...(次のcouplet 1行目).God heard......
[B]:To Jesus christ he called to (couplet 2行目)
.....(次のcouplet 2行目)
Our lord heard....
[F]: To Jesus he called soon (couplet 2行目)...
(次のcouplet 2行目)
And soon was heard his prayer
その時点から時間が経過した
物語詩の中で小鳥たちの会話文("3行")には神は聞いたの..herad..を繰り返さずに
God (Jesus Christ)..has heard ...と現在完了を用いている。
★現代英語における現在完了の用法には「完了」「経験」「継続」の3用法がある。
『 完了:I have now arrived at the close of my story.
(今や物語の終わりに来た。)
経験:I have seen many great men in my time.
(私は今までにたくさんの偉い人を見た。)
継続:This house has stood here for the last ten years
(この家はこの10年ずっとここに立っている。)
研究社 第5版 新自修英文典 USE OF THE PRESENT PERFECT p.310-312
から引用 』
前記
中期英語原文[F版は]now を用いているので現在完了の「完了」が適用できる。
[E版]に for 4 days を補うと「継続」が適用できると仮定する。
[B版]に once を補うと「経験」が適用できると仮定する。
しかしこのような強引な字句の加筆は改竄であり
The Seven Sages of Roma ローマ七賢物語は
中期英語原文のままの形について研究する他にないとされている。
☆ 原文の共通語彙は1詩行中の cryde, called,そして行末で
sone,soone (soon) と同韻語になるための
bone,boone (boon) である。
内容は神の恩寵、恩恵、賜物、ありがたいもの、頼みごと、利益、etc.
これは神学的問題で物語の虚構性、真実性よりも表現の余地が狭く
読者にも判読を要求している。
第15物語において
海の鳥類が[B版 3423:
前ページ:E,F版も参照]
"Child, thynke not this tym longe"
(子供よ、この時をそんなに長い時間であると考えないように(今回はもう長くないと思い給え))
《this life: この世、 this time: 今度》
かつて神の恩恵を受けて祈りを捧げるという素朴な信仰を退けるように感じ
ME期(中期英語期)の作者の不思議な情感に肉迫するのはこの時だ。
人間の死が神と世界の果てなしにはあり得ないことを思いながら生存を求めることも
不可能な極限な島という設定は
それほどの瞑想を物語の主人公にはさせないものらしいが
人間と宗教=ある神の関係
を気づかせるに足る要素があり
それを追体験することに不信と低迷する恐怖が生じるのだ。
物語の結果は決して無視できない読者の概念さえ
すっかり形成してしまうある一定方向に誘うのかもしれない。
概念をくずすものは無知ではないはずだが
さらに至上性を求める心は宗教心だけに傾斜し
世俗の苦しみを容易く分離させる力ある慰めへと転化させてしまう。(1985年に書いた文章そのまま)
2025年に改めて疑問が生じたのは、"Child, you think not too (so)long"
直訳「そう長くはないだろう。」を児童文学のように訳せないかという事だった。
C版
3884-6と照合すると『
日本語は金子健二博士訳』
And said:"Childe, gif þe noght ill;
(
And said "Child, you grieve not ill;
子供さん、悲しむんではありませんよ。)
Ihesu wil þe help in haste;
(
Iesus will you help in haste;
『イエス様は直ぐ貴殿をお助けになりますよ。』
)
Þi meschefe es now
alþermaste."
(
Your mischief is now altar mast.
『あなたの不幸は今は一番上りつめた所なのです』)
中期英語:alþermaste
の意味は一語を分解して
altar :祭壇
mast: マスト、帆柱、とすると祭壇の一番上の柱?
all there mast :そこにあるのはすべてマスト?
C版はより抒情詩的ではあるけれども
4版すべて海中から陸へ上がったものの
(C版は海上のある島:Opon ane ile þere, in þe se.この行は中期英語のþe=the
を視覚的に配置している。)
餓死寸前だったという意味である。
子供は了解して神様に感謝すると5日目に漁船が陸の近くへ来た。(C版:biside þe land.)
E,B,F版:岩(the roche)の近くに来た漁夫は30マイル先の城の代官に20ポンドで子を売り代官夫妻は子を愛したまでの写本箇所(原文のまま)について
野鳥が歌った後海路が凪いで静かになると直ちに一人の
漁夫が来た(a fisser com)のは神意(godes will)の如くであった。
(
[F 2618:And soone aftur the wordes stylle,]
[E 3326: Soon after by that place so wilde]
[B 3426:Anon after as it was godes will]
)
☆聖書と比較:
’Thy will be done ’
(みこころが行われますように)
『聖書 マタイ Matt.?』
新約聖書 マタイによる福音書 第6章
10."Your kingdom come,Your will be done on earth as in heaven.
(『御国が来ますように。みこころが天に行われるとおり、地にも行われますように。』
11. "Give us today our daily bread.
(『わたしたちの日ごとの食物を、きょうもお与えくだい。』)
『国際ギデオン教会 日本聖書協会 和英対照より引用』
ローマの七賢物語 "The Seven Sages of Rome" を読む時
中世の写字生が聖書の記述を共通要素としていることを飛躍とは思わない。
なぜならばD版ミッドランドバージョン:
王妃の第9物語 バージル (Virgilius, Virgil)には
E,B,F版にはない語彙:"gospel" がある。
D版 1954-1955
The Emperour was payed ful wel,
(The Emperor was in perfect content,or
was very well pleased, or satisfied,
皇帝はとても喜んでいた、十分満足した、大満足だった。)
And wende hit were al gospel
(And believed it were as true as gospel
そしてそれを福音のように信じた。)
gospel の意味は福音;
通例 Gospel: 聖書の福音書:the Gospel according to St.Matthew,Mark.Luke,Juhn
(マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝の中のー)
al gospel :in the same way as gospel福音と同じように。この比喩をローマの七賢物語ーバージルで用いた場面は
ローマに立つ魔法の鏡付き柱を破壊せよというItaly,Pule,Apulia,王の命に従って
2人の学者がローマタウンに来て地中にあらかじめ埋めておいた
金銀宝石box を発掘したとローマ皇帝に見せた時彼はそれに目が眩み信じてしまったという
箇所である。
第15物語
「予言」の子供は神のもとに召されず死なずに
生きることができるのだった。
漁夫が岩の近くへ来て晴れやかな表情の幼い子供を見つけた。
子供が「神様は知っていた。」
[E 3328: And saye the chylde, god hit wote.] と言うと
釣り師は彼のボートにその子を乗せた。
それからそこから30マイル(
E: xxx myle, B: Thirty myle)
の所にある堅固な城(
E: a castelle a welle stronge pyle,
B a castell stronge, F:a castell strong,)へ導き
そこでその子を素早く(
so snelle)城代
(
E:the constabylle, B:the constable, F: the steward)に
20ポンド(
XXpoundeで売った。
慈悲深く高尚な城代と妻は彼をたいそうかわいがった。
その時その国に一人の王がいて大変な朝を引き起こしていた。
(
E版 3339: That makyd myklle mornynge,)
3羽のカラスが昼であろうが夜であろうが馬であろうが徒歩であろうが
王の行く所どこにもつけて来て王に鳴き叫んでいた。
その王が平和(安穏)に暮らしていない
(
B 3443:That nyght ne day no pees he hade:
That night no day no peace he had)
のを見たすべての人々がカラス達の叫びを大変不思議がった。
皇帝はカラス達の鳴き声が何か前兆を意味しているいるのだろうかと
彼の国(land,country)の最も賢い人を求めて彼は或る日使者にメッセージをもたせてやった。
下記はその原文E版:3343-5
What myght betoken hyr cryyng (What might betoken their crying)
And apon a day he sente hys sonde (And on a day he sent his messenger)
Aftyr the wysyste man of hys londe (After the wisest man of his land)
これに答えて城に参じた者は(the wisest man of his land :賢人達以外)
barons (男爵、王の直臣,貴族)・・・E, B, F ,C 4版共通語彙
lordys,lordes (lord :中世ヨーロッパの封建領主 大名) ・・・E,B,C版共通語彙
knght,knygtys (knight: ナイト、中世騎士)…E.F 2版共通語彙
euerychone (everyone すべての人)・・・E.F版共通語彙
B版のみの語彙
cownsayll (counselor: 顧問、相談役)
squyre (squire: knightよりも低くgentleman よりも高い地位,地方のジェントルマン、
騎士の従者)
constable (《英歴》城守、城代、)
F版のみの語彙
steward (執事、家令)
中期英語 baron と constableのスペルは現代英語と同じである。
『constable ☆今も次のような官名に残っている。
the Constable of Windsor Castle ウィンザー宮管理長官、
the Constable of the Tower ロンドン塔管理長官
<研究社 新英和大辞典参照>』
B版にはこのお城の場面にthe seven sages 七賢物語の典型的な登場人物である騎士がいない。
knightに近い同意義語はmany a squire である。
この中期英語のsquire:スクワイヤーが現代アメリカ英語では
『地方都市で治安判事(justice of the peace)or
地方判事(local judge)などの敬称となっている。
研究社 新英和大辞典参照』
D版と比較すると
D 3214-5 To aselen a comuyn parlyment
(To convoke a parliament under seal
『封印の下に議会を召集するために DeepL機械翻訳』/
To wyt conceyl of ham alle
(To know counsel of them all
彼ら?全員の助言を聞くために)
3217:
The warden of the castel(castle)(城の門番)/
3222:
And the pepyle al come (And the people all come
そして人々は皆やって来る。)
Dは上記のE,B,Fに比べると城の番人:warden(one who is in charge of a castle,guardian
)ばかりが強調されてあまりファンタジーでない。
Dが用いた語彙parlyment(aseembly,会合,parliament,議会)は
C版と共通である。
3950:『And gert ordayn a grete parlement そして一大会議を開かせました。金子健二博士訳』


新訳 ミッドランドバージョン、Midland Version と比較