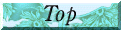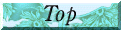……私は3羽のワタリガラスを見て笑ったのです。……
3159-66
和訳ページ第15物語参照
鳥たちのさえずりで言ってた事は/
彼らが船尾に止まるや否や/
私はこれからそうなるはずだと/
偉大な権力を持つ人間になり/
どうでもあなたの好きなようにしたらいいのです。/
私の両手に水を与えるために/
そして母は喜んで急ぎ/
私の両手を拭くタオルを持って来るのです。/
予言のモチーフはギリシャ語版シンディバード物語のラストで王子の師
Syntipas(シンティパス)が語る物語にも見出される。
Stephen Belcher がこの物語をVaticinium のバージョンとして列挙するが
実際には予言の主題だけに類似している。
(Belcher, 伝播,(p.50, n.74))
この物語はある賢者の息子にまつわるもので
占星術師によれば15歳で泥棒になる宿命にあるという。
父親は息子に優れた教育を与えることでこれを回避しようとするが不可避的に
占星術師の予言は的中してしまう。
(このアウトラインは与えられた要約から引用したものである。
Chauvin,Biblographie,p.70,
"Le voleur predestine"という題名がつけられた。ギリシャ語原文の翻訳はない。)
このストーリーはthe Seven Sages (七賢物語)のオリジナル校訂者によって
Viticinium(予言)の選択に影響されているかもしれない。
実際に一体どんなバージョンであったかは校訂者に知られて
依然として不明なものそこでは運命が等しく重要なのである。
シンディバード物語の他の現存バージョンは今でも王子によって語られる
共通の(通俗的な)物語
"Lac venenatum"において運命の役割を強調する。
(このストーリーはシリア語、ギリシャ語、古スペイン語バージョンに現存する。
"the Seven Vizirs", "the Sindbad-Nama" と同様に。)
3163
That thou schuldest by glad to fonde
(That you should be willing to concern yourself,
or be pleased to busy youself
『自分自身に関心を持つことを厭わないことだ。』or
『貴方が忙しくしていることを喜ばなければならない。』
DeepL機械日本語翻訳
3167-8
The faders hert was ful of pryde.
(The father's heart was full of pride.
この父の心はプライドに満ちていた。)
And thout yht schulde nougt so bytide,
(And thought it should not so happen,
そんな事が起こってはならないと思っていた。)
この父親の自尊心に対する洞察はD版ならではのものだ。
その他のバージョンでは
父親は息子を海に投げ込む前に
彼の偽りを証明してやると言う。
3170
And threw hym into the salt flod.
(And threw him into the sea,(salt flood)
そして彼を海の中に(塩の満潮)投げ込んだ。)
Viticinium はまた長いロマンス物語の中でも
子が父親をいかにして殺せるのかを予言する沢山のエピソードと似ている。
Alexander アレクサンダー in several accounts (歴史漫画動画):
Edippus in the Thebes テーベのオイディプス王:
Lydgate (リドゲート) によって書かれたテーベ包囲戦:
The Excidium Troiae: (作者不詳の短い写本:エクシジウム トロイア;トロイの破壊)
に由来したストーリー:(中英語詩 トロイア戦争:The Seege or Batayle of Troye)
ギリシャ神話のTelegonus テレゴノス in several accounts (歴史漫画動画)
Troy Book /
Destruction of Troy,/
Judas in Titus and Vespasian.(ユダヤ戦争: ティトゥス・フラウィウス・ウエスパシアヌス)/
ローマの七賢物語のVaticinium(予言)における子供のように
これらの息子のほとんどは
予言を回避しようと望んで死にさらされているか
故郷から追いやられる。
しかし七賢物語のVaticinium(The Prophecy)において
親殺しのthe dark crime :
闇の犯罪は
子供が親よりも豪の者になるというそれほど不吉ではない現実(reality)によって
象徴的に置き換えられ読み替えられる。
このような代替えの道筋は王子の物語にふさわしい。
王子自身を死刑にしないように父親に説得しようと努めたのだ。
3171-4
When he was in the se kast,
(When he was cast into the sea,
彼が海の中に投げ込まれたとき)
To dye he was sore agast,
(To die he was greatly terrify.
彼は死ぬほどひどく怖がった )
The wynde blew, the se was wod,
(The wind blew, a sea current was turbulent,
風が吹き海流は荒れ狂い、)
And bare the childe into the flod.
(And carried the child into the sea.
子供を海中に押し流した。)
子供の恐怖と悪天候を描写したこの詩行はD版に特有である。
3175-3181(和訳ページ第15物語参照)
天国に御座す神の助けによって/
彼は直ぐに一塊の岩に近づいた。/
彼は速やかに水中から出て/
1つの岩石によじ登った。/
そこで彼は苦しみをなめた。/
二日二晩/
そこで彼は岩の高所に座った。/
3182
That no sokur he ne see.
(にもかかわらず彼には何の救助もなかった。)
他のバージョンでは
鳥類が彼に付き添いまもなく貴方は助けられるだろうと話しかけたと伝える。
3183:
イエスは彼に一人の助け人を遣わした。
3184-90
7行の日本語訳(和訳ページ第15物語参照):
そこに救い主となる漁夫がやって来たのだ。/
彼が岩の傍まで来た時/
彼の目を上げて見たものは/
固い岩の上にいる子供だった/
それから急いでそこに向かって船を漕いで行った。/
岩まで漕ぎつくと/
彼はその子供を船の中に乗せた。/
子供の救出はC,R 版の方がD版よりも詳述している。
彼は魚師に助けて下さいと叫び
魚夫は彼を憐れんで船に乗せた。
子供は何が起こったのか(What was happened)を話すと
漁師は彼を有名なお城に連れて行ってあげると言う。
3191-4
Thar come a strem that was wode,
(There came a sea current that was turbulent,
その釣り船に暴風雨のような潮流がやって来た。)
And bare ham into the salt flode
(And carried them into the sea
そして彼らを海洋に運んだ。)
So fere fram there the child was bore
(So far from there the child was born
子供が生まれた土地はそこから遠くはなれていたので)
That alle hys knwlech was lore,
(That all his familiarity with things was lost,
彼の同郷のよしみ(親近感)がすべて失われた。)
子供と漁夫の長い旅のデテールはD版ならではのものである。
3193行は
他の原文にも反映されているけれどもそれらは
城がどれほどはるか海の彼方あったのかを距離の単位で書いてある。
古フランス語バージョンA※:30leagues (海上では1リーグ=3海里、1.852km?)
E, B版: 30miles: (1マイルは約1.6km)
F版;ただ単にはるか遠く
3195-3200行 和訳ページ第15物語参照
そして彼らは無事に到着した。/
壮麗な城のもとに。/
漁夫はボートから子供を連れ出した。/
そして直ちに城の中に彼らは入った。/
城の門番に(お城を管理する者)/
それから彼に子供の身一つを引き取ってもらった。
(人身売買をした。)/
3201-3
Anoon aste the childe was knowen,
(As soon as the child was known,
その子供が知られるとすぐ)
He was byloued with he and lowe,
(He was cherished by and was loved by,
彼は慈しまれまた愛され、)
Alle that in the castel were,
(All that were in the castle,
その城にいるすべての人々に。)
この3行は子供の才能を思い出させてくれる。
(前頁Note 3136も参照のこと)
A版とB版のみが城の門番には妻がいて彼女も
子供を愛していた。
3204-3210行
和訳ページ第15物語参照
彼はそこで幾冬を過ごした。/
彼がいたその国で/
奇怪な出来事が王の身に降りかかった。/
不快な鳴き声の三羽のカラス達が/
いつ何時でもぴったりと王様の後をついて回るのだった。/
彼が馬に乗って行く所へはどこでも
あるいは徒歩で行く所へはどこでも/
王国の民は注意を払った。/
3211-3212
The kynge was schamyd therfore,
(The king was ashamed therefore,
国王はそのためにこれを恥じた。)
That hym were leuere ben unlore.
(That he would rather be never born.
彼はむしろ生まれて来ない方がましだと。)
D版だけが王の苦痛と窮状を語った。
3213-18
和訳ページ第15物語参照:
彼の国中に文書による指令が発送された。/
調印されて議会を召集するために/
構成員の助言を得るために。/
王に生じた苦境について(3羽のカラスが王にはりつくという特殊な状態)/
子供を預かっていた城の番人は/
きちんと服装を整えて/
3219
And the child with hym nam,
(And took the child with him,
彼と一緒に子供を連れて行った。)
その他のバージョンでは
子供自らが連れて行くことを要求する。
C版3965-66 『和訳は金子健二博士』
"Sir, said þe child "Þar charite
(said the child "There charity
『貴殿、お慈悲ですから』
Wiltou lat me wend with þe?
(Shall you let me go with you?
『私を貴殿と一緒にお連れになって下さいませぬか。』
3220-3444
和訳ページ第15物語参照:
その国王の議会に参上した。/
会議が召集された時/
あらゆる階級の人々が来て集まったので/
国王はもはや会議を延期しようとはしなかった。/
彼を悲しませたのは何だったのかと国王は話した。/
そして人々にこう申した。/
「誰か私に語り得る者はおらぬか、/
鴉たちが私に叫ぶそのわけを。/
私の不面目にひそんでいる意味を露わにできる者がいるならば/
カラスはもはや叫ばないように。/
カラスはなぜ泣き私は恥ずかしさを感じるのであろうか?/
私は私の領地の半分をその者に与える/
またその人に対して本当に用意ができている。/
That I may gyf(give),by my lyf(life)『私は命を捧げよう。DeepL 機械翻訳』/
そして私の娘をその人物の妻として。/
城から帰って来た子供は/
カラス達の言葉がわかり/
その知性は神が彼に授けたものだった。/
鳥たちの1つの言葉を彼は知っていた。/
子供は彼の師匠に相談を切り出して/
言った。「先生私は/
真実を語れるのです。/
何故カラス達が騒々しい叫び声を発するのかを/
そして王様をカラスたちから解放するのです。/
三羽すべての不愉快極まる大きな叫び声から。/
3245
"Sone", he sayed ,"yf thou art bolde
(Soon, he said,"if you are bold
直ぐにと彼は言った。「もし貴方が勇敢ならば)
A, C, R版では
門番が子供に
カラスに関してもし間違っていたらどうなるのかを警告している。
C版例:
『和訳は金子健二博士訳』
Þe steward said:"Lat swilk wordes be,
(The steward said:"Let such words be,
『代官は申しました「そのような言葉はここだけの話にして置くがよかろう)
For, son, þou may sone shend me;
(For ,son, you may soon destroy me;
『という訳は貴殿はそれが為に直ぐ私を自滅させることにならぬとも限らないから』
If þou told a wrang resown,
(If you told a wrong reason,
『すなわち万一貴殿が誤った理由をお話しでも致すことがあれば』
In eyly tyme come we to toun
(In every time come we to turn.
『私達は飛んでも無い不幸な目にあうのだから。』
D版
3246-3260
和訳ページ第15物語参照:
貴方が言った事を実行するがよい。/
国王のもとに私も行き/
貴方は名乗り出て務めを果たしなさい。」/
「師よ。」直ちに彼は言った。/
「ご心配なく私達の仕事の全精力を発揮しましょう。」/
彼の師はすぐさまその道を選んだ。/
そうして彼は国王の前に歩み出て/
言った。「我こそは容易に語ることができる者です。/
何故三羽のカラスが王様の頭上や側面で鳴くのであるか。/
それは陛下に恥辱を与えていますが、/
私が彼らを群れをなして飛び立ち去らせましょう。/
陛下がお約束なさったことをお守り下さるのならば。/
国王は子供を一心に見つめました。/
そして一瞬素晴らしい愛の瞬きをして/
3261
And sayed "Certis that haue het:
(And said "Certainly that have promised:
確かに約束した。)
主語代名詞の省略の例である。
[I]を補うと
(And sayed "Certis that [I] haue het:
(And said "Certainly that I have promised:
確かに私は約束した。)
3262-68
和訳ページ第15物語参照
私は誓います。さらにまたより良い善事を成し遂げたい。/
一団の男爵あるいは貴族たちの面前で/
その結婚を国王は彼に認めた。/
彼は跪いて国王に敬意を表した。/
そして彼の談話を始めた。/
「国王陛下、陛下が御覧の如く、/
あそこに三羽のカラスが立っています。/
3269
Twa males and o fmel
(Two males and one female
二羽はメスで一羽はオスです。)
[....数行欠、写本に空白無しだが........]
その他のバージョンにおいて
子供は二羽のオスのうち年長者がメスを伴侶にして保護してきたと説明する。
『そしてこれがD版の欠落した行の意味である可能性が高い。
DeepL機械翻訳。』
D版の(3269
Twa males and o fmel)は
フランス語バージョンの
C'est une corbe et II corbiaus
(C'est une corbeau and II corbeaux
一羽のカラスと二羽のカラス達)に類似している。
他のバージョンではくだくだしく書き連ねてあり
その詩行において
一羽で座って鳴いている鳥はメスで
他の二羽はオスであると子供が言う。
3270
That o rauen was ful holdr;
(That one raven wa very old;
オスのうちの一羽はとても年をとっていた。)
ライト博士(Thomas Wright ,1810-1877)版は
That to :
OED(古英語辞書)はThat to
という写本の読み方は
That o 或いは The to に対するエラーとして引用する。
Jill博士はThat o とこの行を校訂した。
o は one の例は前の行に見出せるから。
Twa males and o(one) fmel