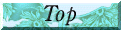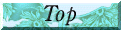第12物語:前ぺージ Note2560行までの大意:
一夜番の騎士と婦人が抱き合っている間に..../
盗人の一人が絞首台から消えた.../
チャペルへと彼は急いで馬を疾駆させた。/
そして小屋に戻り彼の苦痛を訴えた。/
「嗚呼、悲しいかな。/
私が見張っていた一人の盗人がいないのだ/
だから私は大変びくびくしている/私の所有地が失われやしないかと。/
・・・・・・・・」/
婦人はその時答えた。/・・・・・・・/
「私たちは貴方の(彼女の)シェリフの墓に行って/
直ちに死骸を掘り出し/
2562
As fayer as the othyr dyde."
(As exactly as the other dead body.
他の死体(闇の中に消えた絞首台の一人の死者の肉体)と全く同じように。)
D版は遺体を掘り起こすという猟奇的な事は何も書かれていない。
F版において
騎士が死体を墓から掘り出すことを拒んだので婦人は自分で掘り起こし
それから絞首台まで背負いそしてそれを吊るす。
その他のバージョンでは
騎士は遺体を掘り出すことに反対しないが
絞首台に吊るすことは拒否する。
(そんなことをすれば彼は臆病者とみなされるだけだと
ただひたすら言いながら。)
それで婦人は消え去った盗人の死体の代わりに彼女の夫の屍を吊るしたのである。
2581
"Sire," quod scho tho, "therof al
("Sir," said she the, "thereof all
サー、その時彼女は言った。「すべてのソースから)
[.....数行欠.......]
[....写本に空白はないけれども...]
2581までの大意:
八方塞がりの場所で
3人の盗人が絞首刑で死んでいたのだ。
そのうちの2人のうちの1人の死体に大きな傷痕があった。
彼が見つかってもそのような傷がなかったら
その時見張り役の騎士の土地は失われ殺される。
恐らく婦人は夫の死体に傷をつけるよう申し出てそうするために
準備する。
D版....(彼女は騎士に貴方の持っている剣か短刀を抜いて死体に同じ傷痕を付けなさいと言うと
「私に全くの災いが降りかかるはずだ死んだ男を突き刺すくらいなら、、、」と拒まれたので) 婦人は彼女の外套からナイフを抜く。
その他の版...彼女は騎士の剣を取る。
2582
And drew a knyf out of hire schete,
(And drew a knife out of her cloak, ronbe
そして彼女のマントからナイフを取り出した。)
OED(古英語辞書)は
schete を sheath と注釈する。
しかしschete はこの語形の唯一の例として挙げられている故に,
(この意味で語尾に-th(e)がないのは珍しい。 )
またこの行は hire scheteと読むので
Dr.Jill Whitelock はこの語句を
"cloak,(緩い袖なしの外套、マント、) robe
(衣、おおい、ローブ)
と注釈した。(MED 中期英語辞書はこの語句を文証した。)
(婦人は鋭利に研いである尖ったナイフで
夫の頭に一つの傷を作った。)
2586
And syed, "Sire, wel we goon,"
(And said, "Sir,we fare well.
そして言った。「サー、私達の事はうまく運びます。)
この時点でYグループ原文(F版を除く)は
騎士が婦人の本性を見過ぎてしまったと我ら読者に言う。
A版:
2697-8
Þanne þe kniӡt wel vnderstod,
(Then the knight well understand,
その時騎士はよく理解した。)
Þat fals and fikel was hire blod
(That false and deceitful was her blood
彼女の気質は人を惑わし欺瞞に満ちていた。)
(誰かが担ぎ去ったかもしれない絞首刑の死体には
2本の前歯がなく彼の顔は私の記憶と一致しないので
私は殺されるかもしれないと一夜番の騎士が言った。
婦人は叩いて2,3本抜き取りなさいと頼むが
彼はヨハネに誓って1本さえ砕けないと断った。婦人は
聖マリーに誓って石を一つ彼女の手に掴み..次行
)
)
2600
And knockyd out two teth anoon,
(And knocked out two teeth at once,
歯をノックして一度に2本の歯を折った。)
F版にはさらに事件がある。
それは騎士が言うには
姿を消した一人の死体には指がなかった。
そこで婦人は剣を取り夫の遺体の3本の指を切り落とした挿話である。
2601-8
8行の和訳:
サー、彼女は言った「彼の首より上の部分(頭)を変えよう/
急いで私たちが成功したことを/
彼は或る人になぞらえて描かれた/
夜が明け白む程に/
彼等はすぐに死体を運び出した。/
そして絞首台へと歩き始めた。/
そして同じ位置に吊るした。/
ちょうどそこでもう一人が死んだのだ。
この結末はD版独特のものである。
その他のバージョンにおいて
騎士は婦人の遺体に対する
振る舞いを理由に婦人との関係を拒絶する。
2625
To bede a euen when scho cam,
(To bede a evening when she came,
彼女が晩に寝室に来ると)
古フランス語バージョンA※
C,R版の物語は翌朝に語られる。
2635-8
2635:
Thay wylle gyle the wyth hare werke
(They will deceive you with their works
彼等はその業であなた方を欺く。)
第13物語ローマの前置きはその他の版と異なり皇后が皇帝に"the Feast of Fools"
(愚人祭:主に中世期フランスの教会内で行われていた
1月1日のばか騒ぎ・・・ 参照:研究社 英和大辞典)
を祝う理由を尋ねている。
しかしこの意図は多分
1月:January に
Geneuer という学者の名前をつけたのかという後の論及に連結している。
(次のnote)
"The Feast of Fools"は二度と語られない。
(参照:Brunner, p.222. notes I.2738,&
Campbell.Saven Sages p.179,
notes Ⅱ 3057 3058)
2636
As dyde Geneuer the clerke
(As did Geneuer the scholar
学者のジャニュウエリーがしたように)
その他の原文; Gyneuer, /
古フランス語バージョンA※、
中期英語 F,C,R版: Genus/
A版 Gemes /
B,E版 Junius, Junyus/
Ar版 Julius/
D版にある名前の形は Geneuer が年の初めの月に
自分の名前を付けたという俗信を反映している。詳細はD版以外
全てのバージョンに書いてある。
Ar版においては
学者がJulius ,ユリウスと呼ばれているので彼は自分の名前を7月に
July と付けたと言われるようになった。
E、B版において
学者を Junius と呼んで
彼等は彼の名前は1月 January に付けられたとまだ主張しているが。
2537
That with qweyntyes and with bost
(That with cleverness and with noise
『それはノイズを伴う巧みさである。DeepL機械日本語訳』)
2638
Schend the kynge's' and h[are] hoste.
(Bring about the death of the kings and their army.
王達とその軍隊を煽動して死をもたらした。)
ローマには3人の異教徒の王がいた。
従って行間書入れ語句...
kynge→kynge's'
所有代名詞 his が未修正のままになっていたが、
Dr.Jillの校訂は、 h[are]their
2733行例文は
Dr.Wrightによって修正されずまた行間書入れ語句はない。
Thre kyngys and hare hoste
(Three kings and their army.
3人の王と彼らの軍隊)
★
皇后の第13物語
2645-739
Roma ("Rome" ローマ)
2647
And sayed, ”Thre haythyn kyngys thay come
(And said, "Three heathen kings they come
3人の異教を信仰する王達がローマを侵攻する。)
D版の特徴は、7人の王の代わりに3人の王である。
2650
And agayed Rome aftyr thayr lawe,
(And governed Rome in the way of their law.
それでローマをその法に則って統治した。)
agayed・・・
具体的な定義は"ruled. governed, (a city)"
都市を支配する、統治する
MED(中期英語辞書)によってのみ引用される。
関連動詞の項目には gien , agien ではない。
七人の学者がローマにいて異教徒たちの
策略の真相を見抜く力にもなっていた。
昼夜その都市は間違いなく守られていた。
2659-60
On rther was that was bolde,
(One of them that was old,
7賢者のうちの1人は老人だった。)
And sayed, "We been in thys cite.
(そして言った。「私達はこのcityにいる。)
D版は古フランス語バージョンA※に従いその他の中期英語版では
話す老人は七賢人のうちの1人ではない。
2666-7
Lete me haue the laste daye,
(Let me have the last day,
私を最後の日にしてください。)
And fonde to do what I may
(And try or strive to do what I may.
そして私にできることをしようと努力する。
)
ローマを救う最後の賢者でありたいという
長老Geneuerの願いはD版に特有である。賢人たちが
それぞれ1日だけローマを救う任務を負うのも
D版のほかにない。七賢人各々が王子の命を1日救うために皇帝に語る
枠物語を反映している。
古フランス語バージョンAにおいて
賢人達は毎日順番にローマを救うことにもなっているが
これは7か月間cityの食料が不足するまで続くと書いてある。
D版2673-6
And dyuysyde at the laste
(And interpret at the last
そして最後に解釈する。)
A gyn that made ham alle agaste,
(And device that made them all terrified,
彼等を恐怖におののかせる仕掛けを)
And alle was of hys oune thought,
(And all was of his own thought,
すべて彼の熟考の賜物だった。)
And woundyrlych hyt was wroght,
(And wonderfully it was wrought.
そしてそれは,ワンダフルに(訳例:魔力のあるデバイス:下記C版では訳さない語彙wonder参照)入念に作られた。
)
その他のバージョンはこの時点で
彼の発明装置を明かさない。D版は
翌日のために説明しないでおくのだ。
2679-80
He comaunded alle with mouthe
(He commanded all with orally
彼は全部口頭で指揮した。)
Arme thaym a[s] wel as they couthe
(Aemed themselves as well as they could
できる限り武装して臨んだ。)
D版は古フランス語バージョンA,
中期英語版F,C,R,に従い
Geneuer(賢者ジャニュエア)はとりわけローマ人達に武装するよう命じるリーダー
である。
Ar,E,B 版において彼はサラセン人に戦いに備えて覚悟せいと言う。
2680
a[s] wel as (MS 写本:al wel as)について
D版の構成は'as----as'(…に比べて、…同じくらいに)の
通常構文である。それ故 alをa[s]に修正。
als が "as" である構文は下記の行でも見受けられる。
2442:
Ryght als God Almyghty bade,
(Right as God Almighty bade,全能の神のように正しい、
)
3015:
Alse he sat in mornynge,
(As he sat in worry, or anxiety<,
彼は心配そうに、or 不安な気持ちで座っていた。)
しかし上記のals も alse もD版においては
"as ____as" 構文では見つからないので
Dr.Jill Whitelockの校訂は 写本al は al[s] よりも a[s] の方がよい。
2684
Into the heyghest tour on hyghe,
(Into the highest tower aloft,…彼は登った
最も高い塔の上に)
塔の名前
古フランス語バージョンA※.....
Cressant
中期英語E版.....Crassus
B版.....Cressus
Ar版....Carfus
F版.....Gressus
C版 & R版 &D版 ....名前をつけない
これら綴り字の異なるタワー名(発音例E:クラッスス)はこの詩
の序盤で次のように登場する。
第5物語 副題Gaza....Cressent (宝塔の名前)
第9物語 副題Virgilius ....Crassus(皇帝の名前)
2685
And dyde oppon hym a wondir tyre-
(And decorated on himself a wondrous or marvellous outfit-
そして彼はワンダフルというより奇怪な仮装衣裳を自分自身に着せた。)
その他のバージョンで彼のコスチュームを詳述する。それはリスの尾で覆われた衣服と
1つ又は2つの仮面だった。
C版とR版は最も細部に拘泥した。
C版:3102-12『日本語は金子健二博士訳』
A garment to him gert he mak,
(A garment to him decorate he make,
彼は一つの衣を作らせた。)
Side and wide and wonder blak
(Ample and wide and wonder black
それは大きな幅の広いそして黒い衣でありました。★博士はwonderを逐語訳してない。黒いガーメント(衣)=訳さないwonder、
…のような黒色、比喩の例ならば鴉のように黒い)
He gert it dub, fra top til to,
(He decorate it down from top till to
彼はこの衣を上から下まで飾りました。)
With swerel tailes ful blak also,
(With squirel tails full black also. 同様に非常に黒いリスの尾をもって
)
Þan gert he ordain a vesere
(Then decorate he ordain a visor
次に彼は一つの仮面を作らせました。)
With twa faces and fowl chere,
(With two faces and birds or fowl cheek,
それは顔が二つある仮面で鳥の顔をした)
With lang noses and mowthes wide,
(With long noses and mouths wide,
長い鼻、大きな口)
And vgly eres on aiþe;er syde,
(And ugly ears on either side,
醜い耳が両側に)
And brade ilkone als a sawsere;
(And broad each one as a saucer;
然も各々の眼は皿の如く大きく)
With brade tonges and bright glowand,
(With broad tongues and bright glow,
舌は大きくまた異様に輝き)
Als it war a fire-brand.
(As it were a fire-brand.
恰もそれはたいまつの如くでありました。)
ここで一区切り。残りの原文はページが欠けているために失われている。
D版
2687
In the othyr honde a swerde he tooke,
(In the other hand a sword he took,
もう一方の手に彼は剣を持っていた。)