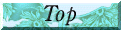2688
As tellys the Romauns booke,
(As tells you in romance language book,
ロマンス語の本に書いてあるように。)
その他のバージョンにおいて
Geneuer ジェネウアーはトリックの一環として
鏡も取り扱う。
2692
As al the worlde schul todryue,
(As so the world shall break into pieces,
世界は粉々に裂け散るように。)
[......少なくとも1行欠落。......(写本に空白はないが)...]
エリジョンの別例:
schul todryue について
schult の語末のtは
todryue
の最初のtから供給される。
他例1928:stille a ston (still as stone
石のように静止)
古フランス語バージョンA の原文は次のようになる。
Lors conmenca à ferir des II espees et
à fere une escremie et une si fiere bataiile
que li feus et les estancelles voloient des espees
(大意???:その時二つの種族間で一戦の火蓋が切られ
フェンシングそしてそれほどひどい戦いがあり
戦火、そしてles estancelles は espees を要求した。
古フランス語の語彙は???)
2712-13
And hare gode hys of grete myght,
(And their God is of great might,
彼らの神は偉大な力を持っておられる。)
And hys into erth lyght-
(And descended from heaven into earth
そして天国(地獄)からこの世(現世)に降り立ったのだ。)
D版は古フランス語バージョンAに倣い中世ヨーロッパのサラセン人達に信じさせたのは神が
キリスト教徒に代わってイスラム教徒たちと戦うためにやって来たという学者Geneuerのトリックだった。
B、F版においてはGeneuerはイエス(キリスト)と間違われる。
Ar版においては悪魔と間違われる。
C,R版においては彼を神の使いの天使だと考える者もいれば悪魔だと考える者もいる。
2717-18
He wylle sle Syre Mahoune
(Helwill kill Sir Muhammad
彼はムハンマド卿を殺すでしょう。)
And oure othyr goddys ilkon,
(And our other gods each one, そして我らの他の神々それぞれを)
D版は当時の作家特有の無知(
旺盛な想像力)で描かれている。
Sir Mahoune(
ムハマド卿)は神
と呼ばれサラセン人は多神教徒として述べられる。
著者(写字生?)はキリスト教とイスラム教の神を(as one and same)同じものとして
認識していない。
これはケンブリッジ大学図書館所蔵
(
MS :1.17.)に含まれた他の多くのアイテムに保管されている。
the Seven Sages (
七賢物語)は
千差万別の反イスラム的原文と並んで東洋の地理的な書物に加えて
発見されている。(
内容一覧はintroductionを参照))
シンディバード物語に由来する七賢物語という事を念頭に置きながら
(参照:The Book of Sindbad)
七賢物語の存在は写本Dd.
I.17,
東洋に関する対立的な題材の中にある。
(つまり確かに七賢物語の中にアンチ・サラセンの物語が存在すること自体が問われる。)
中世における西洋と東洋の複雑であやふやな関係を指し示している。
"Roma" はシンディバード物語には載っていないが
"Pancatantra"には東洋物の類似がある。
2733 The Kyngys and hare hoste.
(Three Kings and their army.三王と彼らの軍勢を(退散させた。))
古フランス語バージョンA※と中期英語E版以外のすべてのバージョンはその後
賢者Geneuerがローマ皇帝になった物語の結末的暗示を与える。
★
マルシアスの第14物語
2787-3018
Inclusa ("The Imprisoned Wife" 幽閉妻)
ハンガリーに一人の騎士がいた。
夜明け前に彼にもたれかかる女性の夢を見て
何処の誰であったか知らないが目覚めるとあっという間に
彼の愛が彼女に向けられた。
不思議(wondrous)なことに当夜その女性はその騎士の夢を見ていた。
2802
He rode hys way thre wykkes and more
(He rode his way three weeks and more,
彼は馬を御すること3週間以上もの旅をしていた。
)
D版は古フランス語バージョンAを模して
騎士に夢で逢った女性を求めて3週間余り探させる。
その他の中英語版で彼は3か月の旅をする。
(B版では一か月にすぎない。)
2805
Into Puyle than he came
(Into Apulia (Italy)then he came
彼はその時イタリア:プーリア州に行き着いた。
)
全中期英語写本(C,R、Ar版を除く)は
騎士がハンガリーからやって来て南の国 Poile (Apulia:イタリアのプーリア州)
で愛を見つけるという道筋が一致している。
古フランス語バージョンA※において
騎士は"Monbergier"(国名は?)を出発してハンガリーにやって来た。
すなわち騎士の国は"Monbergier "モンベルジェと呼ばれ
レディーの国は"Hungary" ハンガリーである。
C版とR版も他の中期英語版に同じく
ハンガリーを騎士の故郷としているにもかかわらず
レディーの国ハンガリーに着いたと書いてあるのでCとRは
明らかな間違えである。
Ar版において騎士は
"Pletys" に到着する。多分
古フランス語"Plecis"の筆写ミスだろう。
(Brunner, p.223, Note2918 参照:
)
Plecis (Plessis, placis..)は中世フランス文学の地名に多発する。
中期英語D版においては
王子の第15物語"Vaticinium"(The Prophecy, 予言)に
子供の両親がいる地名かつ若き王が住むタウン名として下記のように書き連ねてある。
3327:In the toun of Plecie
3333: Into Plecie
3336: Into Plecie when he was comen
2817
But a mayden and hys wyfe,
(But a maiden and his wife,
彼の妻とチーフガール以外は)
妻の付添いはD特有である。
2818-19
And for he wolde of gyle beware
(And for would of treachery beware
そして裏切りに気をつけよう。)
Hys owen body the key he wore,
(his own body the key he wore,
彼が鍵を身に着けていたのは彼自身の身体だった。
)
城主がドアのカギを肌身離さず持っているという詳細は古フランス語バージョンA※と
中期英語F版にもある。
C版とR版では、
C版例;3348:
And þarof bare þe erl þe kay
(And thereof belly the earl the key
『然もその鍵は貴族の腹にあったものであります。金子健二博士訳』)
この後他のバージョンでは主は戦争に従事していると伝えている。
D版はこの戦争の見聞を違う方法で扱う。
ある宿屋の主人からそのことを聞き主君の前に姿を現すと敵と戦うことを申し出た。
D版2838-60その箇所の和訳参照;
騎士は街の中に入って/
そして宿を見つけてから馬から降りた。/
[....原文空白行.....]/
彼は宿屋の亭主に働きかけ様子を探ろうとして/
言いました。「これは誰の城ですか、/
その城は塔がついているし狭間を完備してあります。」/
「お客様」宿屋の亭主は言いました。/
「聖シモンによりて、」/
この町の領主様のものです。/
きわめていい主です。確かに/
それなのに彼はとても困っています。/
この国にいるある騎士が絶え間なく戦争を仕掛けます。/
しかも2年以上ずっと戦争をしているのです。/
だからそれが彼にひどい苦痛を与えています。/
彼はその騎士の面前では雄々しく振舞っていますが。/
四六時中/
その日が来た朝/
彼は城に向かって道をたどり/
それからかれはその貴族にすぐに会い/
彼は大変礼儀正しく挨拶をしてから/
言いました。「閣下よ、私は参りました。/
閣下が始めた戦争のために。/
閣下の戦争をお助けし/
閣下の戦争を終わらせるために参りました。/
☆
この宿屋の場面はD版のみにある。
この時点で他のバージョンでは宿に泊まる場面なしに騎士はチェスの場面で(後述)領主に
自己紹介する。(中期英語では領主は伯爵である。)
中期英語Yグループでは騎士は領主と共にいる。(D版においては宿屋に泊まった後日
貴族と対面したように。)
しかしフランス語バージョンは、
Li sires le fist herbergier en la vile chiez .I. bourjois riche hom.
(.......auberge en la ville chez .I. bourgeois riche jomme.
・・・町にある宿屋
ブルジョアの金持ちの家である。)
ディティールはここでD版とそっくりな古フランス語散文である。
その他の写本原文において
騎士は領主に奉仕を申し出ると領主は
騎士を歓迎する。彼は戦争の最中にいるため助けを必要としていると言いながら。
従ってD版の騎士はより機略にたけた人なのである。
2821
Bot when wolde comen hyr to.
(But when would comr her to,
彼女の部屋に来た時以外に。(鍵のかかったドアは開かない。)
)
主語代名詞の非表現:
ライト博士版では代名詞を補った。
"Bot when [he...塔の主] would comen hyr to.
2832-3
And by the sygth he wyst hir thoght
(And by the sight he knew her thought;
その姿を見て彼は彼女の考えを知った。)
That was the lady þat he hadde sowt;
(That was the lady that he had sought;
それが彼の探していた女性だった。)
この詩行は恐らく改変したのだろう。
騎士が彼女を見てレディーの考えを知ったというのは意味がないからである。
彼はただ単に彼女を探していた女性として認めたのだ。
以下はAr版1974-5
And þo wyste þe knyӡt, sauns doute,
(And then the knight knew , without doubt,
騎士は疑問の余地なく知っていた。)
Þat it was þe lady bryӡt
(That it was the lady bright
それは明るく輝く女性だった。)
その他のバージョンではハンガリーから来た騎士はレディーに歌いかけると
彼女は騎士と話をしたがっているがあえてそうすることができないと
語られる。C版とR版においてナレーターがその時彼女の主人はと言い足す。
参照C版 3293-4:
He sat biside vnser a tre,
(He sat beside under a tree,
『彼女の良人は近くのある樹木の下に坐していました。金子健二博士訳』)
At þe ches, a knyght and he.
(At the chess, a knight and he.
(彼は一人の騎士(七賢物語に頻出するa knight )を相手に将棋(チェス)をもてあそんでいました。『金子健二博士訳』
)
D版
2839
And took hys ine, and lyght adoune
(And took his inn, and dismounted from a horse
そして彼は宿を取ろうと馬から降りた。)
[.....1行欠...写本に空白はないが
多分同韻語 cam を用いていた。....]
2840
Hys hoste he in councel nam
(His host he took into a consultation
彼は旅館の亭主と相談した。)
2847-50
In thys contre hys a knyght
(In this country is a knight
この国(この物語ではイタリアのプーリア州に位置していることになっている)には一人の騎士がいる。)
That werys on hym day and nyght,
(Who makes war upon him day and night,
彼は昼夜を問わず彼に戦いを挑むものである。)
2849:
And hase done twa ӡere and more,
(And it has done two years and more,
そして戦争は2年間以上にわたって続いている。)
F版も戦争は2年続いた。
And that greues hym ful sore,
(And that cause grief to him very bitterly
そしてそれが彼をひどく悲しませるのだ。)
2851
He man[nes] hym wel ate the knyght
(He behave himself like a man in the presence of the knight
彼は騎士の前では勇猛果敢な男のように振舞っていた。)
man[nes]について:
MED(中期英語辞書)は
現代文になおすと男らしく振舞う、勇気ある行動をするとなる
中英語動詞 man[nes]behave を修正してない形の例として引き合いに出す。
写本(Wright版)は mande behavedと書いてあるが
現在時制(上記 2847-50)の後の過去時制に移行するのは
おかしい。
しかしながら
この行の対左余白(the left margin)には('+')マークがある。
それは訂正の必要性を示すために別の箇所で使用されている。
第14物語; 3011:
And 'he' karf hys mete with hys knyf,
(And 'he' crved his meat with his knife,
彼(夫)はナイフで肉を切り分けた。)
そのようにして
過去時制,mande は現在時制mannesであるべきだったが
訂正が実行されないままになっていたらしい。
2859
Forto helpe the[r]for of thyne
(To help therefor yors,= your war?
貴方の戦争に協力するために。)
thyne(thine: thouに対応する:汝の)
所有代名詞は単独でも成り立つ。
漠然としか分からないが
前の行に戻って参照すると
2858:For were that thou hauest vndirnome
(For war that you have undertaken,
貴方が(プーリアのとある国の領主)が乗り出した戦争のために。)
多分あなたの戦争という真意での「あなたの」という意味だろう。
D版の他の箇所の例は前項1937で記述済。
参考ページNote1937
2860
Thy werre forto hende and fine."
(Your war to end and stop. 『あなたの戦争を終わらせ止めるために。』
or
Your war put and end to. 『あなた方の戦争に終止符を打つために。』
『DeepL機械日本語』)
その他のバージョンにおいて
騎士は領主に本国で一人の騎士を殺害してしまったので彼には
故郷に帰ることがどうしてもできないと説明している。