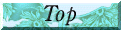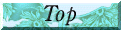3023-8
和訳:
食卓の食事が片付けられた時『ダイニングテーブルが撤去されると DeepL日本語訳』/
彼女は失神のふりをした。/
なぜなら彼女は行動を開始していただろう。/
直ちに塔の中へ行くこと/
そしてまもなく彼女はあちらの塔へ連れて行かれた。/
彼女の夫はそのトリックを知らなかった。/
この女性の気絶したふりはD版特有である。
彼女が主導的に騎士に奸計の進行を働きかけている。
その他のバージョンでは食事が終わると領主は騎士から離れて塔に向かう。その時
騎士は婦人に彼女の国の衣服に素早く着替えさせ彼女を
塔に連れ戻す。夫が塔に到着する前に。
彼女が確かにそこにいるのを見るために。
3029-3038
和訳ページの第14物語参照
プーリア国領主である彼はその時すでにそれを忘れなかった。/
彼はいつも彼女のことばかり考えていたのだ。/
彼が見た不思議なこと故に/
彼は高い塔の内部へ行った。/
婦人の許へ彼が来た時/
彼女は腕の中で彼を抱きしめた。/
彼は大枝に止まった一羽の鳥のように満足した。/
そして皆異常なかったと信じて/
終夜彼女とずっと一緒にいた。/
晴れた日の差す朝まで。/
3039
The styward let take al hys good,
(The steward let take all his goods.
執事は彼の財産を持って行かせた。)
『翌朝、領主は教会へ行き
その間に騎士(執事)は塔から婦人を連れて来て
前日の服を着せる。
彼は領主に結婚の許しを請うが領主は皮肉にも自分の妻を嫁がせてしまう。
DeepL 機械翻訳』
3040-46
和訳ページ第14物語参照
そして海へと荷をになう。/
一隻の立派な帆柱のある船の中へ/
それはすべて新型のように。/
順風が吹いた時に出航するのだ。/
執事は彼の婦人を直ちに連れて来た。/
領主は善良で思いやりのある人間だった。/
それで騎士に彼女を貴族の儀礼で授け行かせた。/
3047-52
和訳ページ第14物語参照
そして彼女を旅に送り出した。/
1 或いは 2マイルの海へ/
トランペットとその他の楽器で/
沢山のメロディーを奏で続ける/
その領主は陽気なさざめきの興に入り/
彼自身で妻を海の彼方に逃してしまった。!/
このように領主が恋人達をエスコートするのはD版だけである。
C版とR版は吟遊詩人(minstrelsy:中世の吟遊楽人の芸、吟唱、弾奏,
『研究社の英和辞典の引用』)
にも触れてるがそれは少し違った文脈である。
C版参照:『金子健二博士の日本語訳』
Þe prest þam weddes swith sone/
(The priest them wedded very soon,
『牧師は時を移さず彼等を結婚させました。』
And als tite als þe mes was done
(And as soon as the mass was done
『聖餐式が終わるや否や』
Þen was þare made grete menestrelsy
(Then was there made great minstrelsy, music.
『大がかりの音楽が其所で奏せられました。』
3052
Tollyd hys oune wyf away!
( He led his own wife away!
領主は騎士に領主の妻を連れて立ち去らせた。)
主語代名詞の非表現の例。
[He]を補う。He はthe lord: プーリア国領主
3053-56 和訳ページ第14物語参照
彼等は離れては行き交い/
親愛なる者の口付けをして別れた。/
船は水域を航行した。/
領主は再び陸に帰る。/
3056
The lord went again to the land
[.....,おそらく同韻語が cam となる1行欠...(写本に空白なしだが)...]
3057:
Into the tour the way he nam;
(Into the tower the way he took;
塔へと彼は道をたどった。)
その他の中英語原文では妻に会って話をするために塔へ行ったと書いてある。
3058-65 和訳ページ第14物語参照
彼は外側も内側も探した。/
それでも塔内部には誰もいなかったので/
そのため彼の心は一気に惑わされた。/
つまり彼の妻が去ってしまった。
執事と一緒に。/
それから嗚呼と嘆いた。/
彼が生まれてからこれまでになかった悲しみを。/
その時彼の喜びすべてを喪失した。/
3066-7
He lepe out of the tour anoon,
(he leapt out of the tower at once,
彼は突然塔から飛び降りた。)
And than brake hys neke boon.
(And then he broke his neck bone.
そして首の骨を折った。)
その他のバージョンにおいて
夫は騙されたと知って苦痛したが
自殺はしない。
.....「皇帝陛下。」とマルシアス師は申しました。まさしくこのように
陛下の奥方も陛下を惑わすでしょう。.......
3079
Certys he schal speke tomorowe
(Certainly he shall speak tomorrow
確かに彼は明日話すだろう。 )
言論と沈黙のテーマは知恵文学に共通する。
王子は黙っているとはいえ
この黙秘こそがその後の彼のスピーチに力強さを与えている。
"The Book of Sindbad"(シンディバード物語,七賢物語の由来)
の結末は特に知恵に重点を置いている。
ペルシャ語版の最後のものにはいくつかの格言(処世訓)がある。
その最後がここに適切である。
Beware of speaking, except on occasions
when they speaking may be useful
So speak, that when thou speakest again,
thy woeds may be the same-may better
(Clouston Sindibad pp 114-15)
発言に注意すること、(話す前に)
話すことが有益である場合を除く。
再び話す時,
あなたの言葉が同じであるように、
より良いものであるように。(DeepL機械日本語)
……明朝祈祷の時間(6時a.m.)
に皇帝は考えた。……
3096-7
In the paleys withouten the halle,
(In the palace without the hall,
宮殿において大広間の外に
)
Thare he lette asembyle alle-
(There he let assemble all-
そこに彼は全員を召集させようと-)
3698
Erlys, barouns, sympile knyghtys-
(Earls, barons, simple knights lowest in rank among a group-
伯爵、男爵、一集団の中で最も身分が低い騎士達を)
他のバージョンでも皇帝は議会を召集する前に教会に行く。
....
その日のうちにギルティー(guilty)となった者たち....
3106
When thay wystyn wat[was] to doone:
(When they were informed of what was to be done,
or what was going to happen, 『その時彼らは何をすべきかを知らされた。
or これから起こることを知らされた時だ。)
[was] はWright博士によって校訂されなかった。
[was] を補うことで
この文章はより理解しやすくなった。
人々は判決が下されると聞くと彼らが何をすべきか知っている時よりも
むしろ集まる。
下記は[wat] [what] を補った例
(Cf. 3384: And tolde me [wat] was to doone.
(And told me [what] was to do 何をすべきか教えてくれた。
)
3120-1
And sayed, "Fadyr, I haue no gyle
(And said, "Father I have no guilty
そして言った。「父よ、私には罪はありません。」)
Of thyng that hys oppon me pute;
(Of thing that is imputed to me;
私のせいにするもの)
repeated 繰り返した行:
3377-8
And certys I have no more gylte
(And certainly I have no more guilty
もう私には罪はない。)
Than he that was in the see pute;
(Then he that was pushed in the sea;
あの時海に押し込まれたのは彼だった。)
上記が示しているのは
D版の写字生がオリジナルの読み方に違いなかったもの
(脚韻:gyle/pyle or gylte/pylte)をよく知らなかったことである。
pylte は普及してない綴り字である。
(MED: (中英語辞書)
おもに南西ミッドランド & 南西 の例として挙げる。
D写字生のダイレクト地域。)
★
王子の第15物語
3134-378
Vaticinium ("The Prophecy" 予言)
ヒーローが故郷から連れ去られる似たようない物語(下記)に比較すると
七賢物語のVaticinium「予言」は短い。
King Horn:
角笛:十字軍ロマンス/
Havelok:デンマーク人のハヴァロック:13世紀中世イングランドロマンス/
Bvis: バビス:1300年頃の中英語詩 /
the Reinbrun section of Guy of Warwick:
ガイ オブ ワーウィックの息子ラインブラン ; 14世紀/
幾編ものConstance romances/
しかしthe seve sages
七賢人のHバージョンにおいて
Vaticinium はロマンス物語の初期バージョンと融合する。
Amis and Amiloun
『アミスとアミロウン』 13世紀後半の尾韻ロマンス
(七賢人トラディションではAmisとして知られる)は
様々な冒険で物語を長引かせる。
(Vaticiniumはもう一つの物語を構成して)その間
ロマンスというジャンルとのつながりを再び強調しながら。
Hバージョンは
中英語による散文バージョンで表され
Richard Pynson,Wynkyn de Worde, William Copland
によって 1493年、1506年、1555年にそれぞれ印刷された。
どうやら
Viticinium と Amici
もゲール語(スコットランド、アイルランドで話される)
伝統の中で七賢物語とは無関係に流布されていたようだ。
(J.G.Mckay 'Canain nan Eun/ 参照)
3134
There was a man that was bolde
(There was a man that was excellent
1人の高尚な人が住んでいました。)
[...少なくとも1行欠...
写本に空白なしだが.....olde]
他のバージョンでは
その人は一人の息子を持ちある年齢に達していたと
伝える。
古フランス語バージョン12歳/
中英語F版 7歳/
他の中英語原文 15歳/
従って欠行末の同韻語はold
だったと思われる。
3135-38
And hadde a vertu that was hyghe:
(And had a unusual ability that was powerful:
そして(並はずれた男の息子は)強力な異能を持っていた。)
Alle men louede hym that hym syghe.
(All men loved him that him saw.
彼を見た者皆彼を愛した。 )
Anothyr vertu Gode on hym layed:
(Another distinction God on him gave:
別に持てる者が凡人よりも高められる心や性格の資質を
神が彼に与えた。)
He wyst wat alle fouls sayed.
(He knew what all birds said.
彼はすべての鳥の言葉を知っていた。)
子供の才能を詳しく解説するこれらの詩行は
D版に特有である。
3138
数名の批評家達が指摘しているように
Vaticinium(予言)の子供は聖書の
ヨセフ(Joseph)を彷彿させる。
両者共予言の力を共有して
その結果二人とも家族から鼻であしらわれ
その後彼らは解釈能力を通じて外国で昇進を得た。
これはthe seven sages :七賢物語の作者が意図をもっていたということ
かも知れない。王子に対する冤罪の事件はヨセフとポテパルの事件
(Potipharはエジプトの役人;
その妻からヨセフが強姦しようとしたと不当に告発された)
に似ている。
それでヨセフの物語の残部を反映したthe seven sages 王子の物語を
書く動機付けとなったのだろう。
3142
A hermete in a roche of ston:
(A hermit in a rock of stone:
石の岩にいる一人の仙人)
D版がフランス語版を最もよく保存している。
それは父と息子が出船したと伝える。
古フランス語版;
por aler à.I.
reclus qui étoit seur rochier (48.002)
(大意:行くために、はるか遠くの隠遁者は岩壁の上にいた。 )
Yグループ原文は島に行くと言っているが
B版以外は旅の目的を具体的に述べていない。F版において彼らは言う。
3453-4
thoght to wynde bothe yn fere
(thought to turn both in far
どちらも遥か彼方の方向にあると考えた。)
Into a straunge Ionde to dwelle there
(Into a strange island to dwell there
見知らぬ島へそこに住むために)
3147
Thre rauenes lyghte adoun,
(The ravens flew down to the end of their boat,
三羽のカラスがボートに飛んで来て端に止まった。)
D版は海上で三羽の鳥が登場する唯一の原文である。
各バージョンの2人乗りボートに降りた鴉の比較
古フランス語バージョン…II corneilles (2羽のカラス)/
中英語E,C,R 版…two ravens (2羽のワタリカラス)/
Ar,B 版…two crows,(2羽のカラス(総称))/
F版…two rooks(2羽のミヤマカラス)/
物語が佳境に入るのはこれよりもっと後の詩行で
王の頭上を追って叫ぶ3羽のカラスの登場となる。
D版:....海にて父と息子が漕ぐ船尾に止まった3羽のカラス達が甲高い声で鳴きしきった……
3149-56
和訳ページ第15物語参照:
その子供は賢く控えめだった。/
そして聖霊のインテリジェンスを持っていた。
(Holy Ghost:三位一体の第三位は聖霊)/
それで一羽の鳥が言ったことの意味を理解し/
彼はそのことに驚愕した。/
そして彼はオールを急速に漕いだ。/
それから父を見て笑った。/
傍に座っていた父親が尋ねた。/
何故また何に笑ったのかと。/
上記の詩行はD版に独特である。
他のバージョンにおいて
父親は鳥が何を言っているのか不思議に思い
子供は鳥の言葉の意味を解釈することができると言った。
D版において父をばかにした子供の笑いは無邪気さと相まって
性格描写のfineな一筆であるが
彼(子)が父に話したのは
彼はいつか彼を超えるだろうという
無神経な言葉だった。