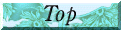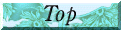3271-4
和訳は第15物語参照:
一時期(穀物飢饉の年)の天候は寒く/
だから彼には少しも能力がなかった。/
彼のつがいのメスのためにほどよくめしにありつくために/
大食のために彼(年老いた方のカラス)は彼女に対して約束を破った。
3275
And bete hys make and droue hire
(And beat his mate and drove away
そして彼のつがいのメスを殴り追い払って彼女は逃げた。)
その他の原文では年長のカラスはつがいのメスを捨てて彼が逃げ去った。
3276-3307
和訳は第15物語参照:
彼のメスは四方八方に逃げ/
彼女の全力を尽くそうと試みて/
勇敢な一羽のカラスと会った。/
その一羽の若いカラスは年老いた鳥ではなかった。/
つがいとなるメスを探し求めていまだかつていなかった。/
それでも彼は彼女を直ぐに彼の相手にすることができた。/
それから方々彼は飛び歩き回り/
彼のメスのために食べ物を十分あてがった。/
寒い天候は去った。/
飢え、冷気そして至極悲しい時が/
老年のカラスは意気軒昂になり/
彼のメスを気がふれたかのように探した。/
そして彼ら2羽がそこにいたのを見つけた。/
彼と彼の伴侶は一緒だった。/
彼は彼女は自分のつがいだと主張すると/
もう一方のオスは彼が理不尽に主張していると言った。/
その理由で彼らは貴殿に叫んでいたのです。/
権力を持っているのは王様だし/
それに彼らは貴方の王国にやって来たのだから/
王である貴方が判決を下すべきだ。/
判決が下された時/
もし永久に貴殿が生きながらえる間/
カラス達がこれ以上鳴き叫ぶのを聞くならば/
即座に私の両眼をえぐり出して下さい。/
どんな時でも彼はどちらかといえば行きたい。/
王は直ちに裁きを下した。/
「なぜなら年老いた鴉は彼の誠実を打ちつついたから/
不当にも己が妻を追い払ったのだから/
私はその判断を下す。/
彼女が生きるために助けたのは若いカラスだ。/
彼は彼が選んだ伴侶を持つことになる。/
そして年長のカラスは妻を所有せずに去り行くがよい。」
3308-9
When the juggement was gyuen
(When the judgement was given
判決が言い渡された時)
The ӡonge rauen schuld ben aboue,
(The young raven should be successful
若いワタリガラス(カラス族の各種?
)が穏当に勝訴した。
)
gyuen と aboue は誤韻である。
写字生が give の過去分詞の原型にこなれていなかったことを示している。
gyuenは ӡoue のような
o を内側母音とする形であったに違いない。
3310-15
和訳は第15物語参照:
国王は彼らをもう再び見ることはなかった。/
彼は子供の話を信じたのち/
彼を己が命のように愛し/
彼の妻にと彼の娘を与え/
そして彼の全財産を法律で定めた通りに
所有する事になった。/
それで彼は国王と共に信じた。/
3316 And ferede swyth myry and wylle-
(And got along very happy and wealthy.
そして幸せで裕福な生活を送っていた。)
予言をモチーフにしたロマンスの英雄の中で
この子供はEdippus(エディプス)
に最も似ている。
エディプスはスフィンクスの謎を解いた後で有名になった。
それはちょうどカラスの鳴き声を説明することによって
子供が宮廷で自らを売り込むのと同じようだ。
このような解釈力の分かち合いがエディプスとの最も重要な類似点であると
思われる。
3316:
古フランス語バージョンA,
中英語バージョンE,F版においては
義理の父の死後その子が王になると特に語られる。
その他のバージョンでは
彼もまた王になったことは明らかだ。
物語の後半でthe messengers(使者達)が出立して
両親に翌日一緒に食事をしたいと伝言する時
彼はその様に言及される。(the king himself....王自身..)
3317-19
和訳は第15物語参照
しかし彼の父は貧乏になっていた。/
彼の本国では実を言うと/
彼は恥ずかしくて住めないので/
3320-1
And wenten thyne, hys wyf and hee,
(And went from that place his wife and he,
その場所から去って行った妻と彼は)
Fer into anothyr countre,
(Fer into another country,
遠く離れた異国の地へ )
『子供の両親は知らず知らずのうちに息子の国に行く。Deepl機械翻訳』
3322-23
和訳は第15物語参照:
そしてそこに住み彼と彼の妻は/
最下層階級の生活を送っていた。/
3324-25
The childe let priuelyche inquere
(The childe let discreetly inquire
子供は慎重に尋ねさせた。
In what town hys fadyr were.
(In what town his father were.
どこの町に彼の父はいるのだろうかと。)
子供は彼の両親が彼の国に住んでいることを知る
他のバージョンでは(CとR版を除き
そのことが夢の中で明かされる。)
そして召使或いは家来達を遣わして王様が
彼らと一緒に食事をすると告げた。
古フランス語バージョンの父の名前はGirart,その息子 thierri(
51.001)
Yグループ原文(
E版以外)
Gerard Nories (
CI 4145),
F版:Barnarde norysshe sone (
EI,3499)
.....
行方を捜しに行っていた彼の従者達によって彼らの居所は
突き止められた。.....
3327
In the toun of Plecie
(In the town of Plessis, France
フランスのプレシータウンで。)
D版(Plessis)のみ古フランス語版の地名を保存している。
va, dit li rois, au plesseiz et demanderas (51.011)
.I. home qui novelement y est venuz
(大意:行け,王の書状を言いなさいフランスのプレセイズで
そして依頼した。貴族然としている人がお宅にお邪魔します。
)
3328-3344
和訳は第15物語参照:
それから家臣達は再び直ちに戻った。/
できるだけ速く馬を走らせ/
彼の足を地面につけて/
言った。「王よ、私は発見しました。/
貴方様がが探し出すよう命じていた尋ね人を/
フランスのプレシーという都市で。」
その息子は立派な身なりをして/
急いでそこへ参った。/
フランスのプレシーの町なかに到着すると/
彼の父の家近くに宿も取った。/
食事に行く用意ができると/
直ちに彼の召使は彼に父の戸口に行く道を教えた。/
良妻にして彼の母の許へ。/
彼が生きて帰還したことを喜ばせようと。/
彼ら従者と王様が家に入ると/
子供はすぐさま水を下さいと頼んだ。/
3345-9
和訳は第15物語参照
すると彼の父は歩いて行き/
水を持って来てあげた。/
しかし彼は直ぐに止められた。/
彼の母がタオルを運びたいと願ったところ/
他の者(従者)はそれを許可しようとしない。/
古フランス語バージョンA※、
中英語版C Rでは予言通りに
父は彼が手を洗っている間
息子の衣の袖をささえてやった。
F版も
"Hys Fadur helde hys oon sleue
(His Father held his son's sleeves
父親は息子の袖を握る。)
彼が手を洗っている間父親が洗面器を持つだろうと
子供が予言したにもかかわらず
C,R,F版だけ
父親が子供をもてなすことを許している。
他の版では
父がそのtask(務め)を遂行するのを止めた。
いずれも子供は母親にタオルを持たせていない。(C版では足軽が手ぬぐいを受け取り王の手を拭う。)
3350-3352
和訳は第15物語参照
子供は迎え入れる作法のあらゆる面を見た。/
それで彼は父と母にぴったりと近寄り/
彼は両手でそのタオルを受け取った。/
3353-65
和訳は第15物語参照:
そして言った。/
「本当に私は貴方様達の息子です。/
父上、今起こっているのは私がカラス達の話すのを聞いたことです。/
私は嘘をつかずに父上に話しました。/
三羽のカラスがカーカーとその鳴き声で言った予言を。/
私は彼らの叫び声を理解したからです。/
それが理由で父上は私を海に投げました。/
しかしイエスがその御手で私を助け/
直ちに私を陸地に導いてくれました。/
あの時私は海で溺れて死にそうになり/
多量の海水に沈みましたが/
そう真に神は私を呪いから守ったのでした。/
今父上は暮らし向きが一層悪いご様子でのおもてなし!」
"Viticinium"(ローマの七賢物語、第15物語予言)の結末に
その子供が父親に言った言葉は
Chaucher チョーサーの
『法の男の物語』(1387年、カンタベリー物語5番目)において
カスタンスが父のローマ皇帝に言った言葉に似ている。
I am youre doghter Custance" quod she,
("I am your daughter Custance " said she,
私は貴女の若い娘カスタンスです。」彼女は言った。)
That whilom ye han sent unto Surrye.
(That whilom you had sent into Surrye,
かつて貴方がシリアに送り込んでいた。)
It am I, fader, that in the salte see
(It's me, father that in the salt sea,
それは私です、父よ塩の海でのことだった。)
Was put allone and damped for to dye
(Was put alone and drowned fot to die
一人きりにされて溺死した。)
3357
What thay sayeden in hyr gaulyng
(What they said,in their croaking of ravens told.
カラスの鳴き声の中で彼らが語ったこと。)
gaulyngこれはMED(中英語辞書) が"gouling の項目で引用した唯一の例。
3366
Than walde the sone speke no mare
(Then would the son speak no more.
それから息子はもう何もしゃべらなくなった。)
[.....ここで1行以上の行が欠けている。写本に空白なしだが。..... ]
他の中英語版において
父親は息子に殺されることを恐れていたからだと語る。
C版:4225-32 『和訳は金子健二博士訳』
When þe fader herd þis tale,
(When the father heard this tale,
父がこの物語を聴きました時、)
In his hert he had grete bale.
(In his heart he had great sorrow.
心の中に大なる悲しみを持ちました。)
Al þa wordes ful wele he knew
(All the words full he knew
彼は是等の言葉の凡てを善く知っていました。)
He was so ferd him changed hew,
(He was so fear him changed hue, complexion
彼は非常に恐怖の念にかられて顔色をかえました。)
He wend his son þan spold him sla.
(He turn his son then should him kill
彼はその時彼の息子が彼を殺すのだと思ひました・・・)
For þat he had hym serued swa.
(For that he had him served so.
彼が先に彼に対してそのやうな事を為した報いとして。)
★Bot þe kyng kissed þam both in fere,
(But the king kissed them both together,
然るに王様は彼ら両人を共に接吻しました、)
★And said:Bese meri, and mase gude chere
(And said: ? merry, and make good cheer
そして申しました。「御心配あるな、元気をお出しになって下さい、)
C版の最後の2行はD版の2行と一致しまずまずの
韻と内容となっている。
C版
3367-8
★And kyst hym and hys modir in fere,
(And kissed him and his mother together,
そして父と母にキスをした。)
★And made thaym swyth fayer chere,
(And treated them very kindly,
そしてとても親切にしてくれた。)
3369-3395
和訳は第15物語参照
つまり彼らに土地と財宝を与えたので/
彼らは肩身の広い暮らしをしたということです。/
皇帝の息子は皇帝に言いました。/
「ここに父上の名誉は全く地に落ちたのです。/
それは熱い血潮がたぎるために
(エモーションやパッションの中枢と思われていた)/
彼の息子を大海に投げ入れました。/
父上よ、父上はその様な気質です。/
裁判という手段を用いずに私の命を奪おうなどとは。/
そして確かにもう罪悪感はありません。/
海中に力一杯押し込まれた彼以上に。/
しかし皇后は私を愛していません。/
だから彼女の考えとは/
魔女の力を借りた魔法と降霊術によって/
私を死ぬべく運命づけるという邪念でした。/
私の師達は月を見て/
私がどうすべきか教えてくれました。/
私が召喚されてからずっとその期間のいつの時点でも/
もし私が話していたら私は死んだのです。/
その上七人の師達も。/
こうして私の幸福は悪魔に伴われた悲運に転じました。/
どんな場合でも陛下は奥様の示唆によりすがったのです。/
彼女は私が死んでいたらよかったのにと願っていましたから。/
そういうわけですから陛下は必ず/
この時に陛下の思う事をするのかしないのか決定してください。」/
皇帝は優しさに満ちていた。
3395
"Dame," he sayed "wat sayes thou?"
("Dame." he said "what did you say?"
マダム、彼は尋ねた 「何とおっしゃったのですか?」)
[.....多分ここで1行のみ欠けている。....
写本に空白なしだが、、、、、]
皇帝が妻を戒める言葉は他のバージョンにはない。
その中で彼は息子が言っている事が真実かどうかを尋ねている。
D版は古フランス語版に酷似している。
Fu ce voirs dame?
dil li empereriz, gardez que vous ne me mentez mie (A 52.009)
(大意:それはよく考えてみなければならない。皇帝は申した。
私に嘘をついていることを用心する我が愛しの女)
3396-3401
和訳は第15物語参照:
皇后の答えの真意を考えてみよう。/
私の頭で。/
お前は十分に非難から身を守ることはできるであろうが/
息子が話したことで私が知った犯罪事実とは如何なるものなのか。/
七賢人は生きているけれども/
お前は不名誉な死を免れないだろう。/
3402-7
The Emperes, sothe forto telle
(The Empress to tell the truth
皇后、本当の事を言えば)
Was combird wit fynde of helle
(Was possessed by an evil spirit (with the Devil of hell, Satan)
悪魔(地獄の王サタン)に取り憑かれていたのでした。)
That scho myght nout forsake
(That she might not deny an accusation
彼女はその罪状を否定はしないかもしれません。)
That let the treson make
(That let the treason make
反逆を企み)
With wychecraft and felonye
(With witchcraft and felony (act of treachery or craft)
魔法
(witch:魔女, wizard:魔法使い,《古》聖賢、(sage))を使って背信,背徳行為を行った事を。)
Forto make the childe to dye,
(For to make the child to die,
王子を死なせるというおもわくで。)
悪魔の憑依という表現はD版だけが持っている。
恐らく中世詩七賢物語で嘘をつき通しだった
皇后が王子が話したからといって
罪を告白するはずがないだろうと校訂者は考えたのだろう。