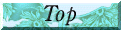注釈296-304 参照
和訳はオープニングプロローグ箇所:
彼女は魔法をかける術を得たのでした。/
それは七日七晩/
王子は誰とも話してはならず/
もしどんな言葉でも発せられたならば/
従者達は彼の弁舌を聞くかもしれないけれども/
直ちに王子の心臓は粉々に壊れて死ぬであろう。/
或いは彼は二度と喋れないであろう。/
この魔法を邪悪な女がもたらしたのでした。/
王子を死に至らしめるために。)/
古フランス語原典にはnigrimancye ネクロマンシー(降霊術、黒魔術etc.)
の言及はない。
C版とR版だけ似たような改竄がある。
皇后は魔女(witch)の助言を得て王子が宮殿に到着してから
7日以内に話すように仕向けるという王子の死を考案する。
C版においてこれは本文の前の方に書かれている。すなわち
D版にはない部分で愚かな僕が
プリンスの事柄を告げ口したので皇妃は妖術師を相談相手にして
王子の7日以内の発話と沈黙の奸計を巡らせたというくだりである。
そのあとで皇妃は皇帝に問いただすと王子の存在を認めて
彼女に会うことになる。
降霊術は明らかに悪魔の魔法だった。
(Richard Kieckhefer : Magic in the Middle Age
中世の魔法 Cambridge ,1989)
そしてこれは七賢物語第15枠物語の最後に彼女が罪を告白するエピソードの意味をなす。
D版では 3403行:
She is "Was combird wit fynde of helle
(She possessed by an evil spirit (with the Devil of hell)
彼女は悪霊に憑かれた(地獄の魔王、サタンと)
ネクロマンサー(死霊術師)が呪文を唱えて呼び出した悪霊(an evil spirit)を制御することは困難であり
中世の説話例では悪霊(Fiend)自身が嘘つきで信用できない召使(servant)として描かれた。
(ibid.p.174 ネクロマンシーに関して上記のRichard Kienckhefer の本を見て知る、禁じられた儀式、15世紀のネクロマンサーの祈祷書 (Pennsylvania,1998)
頭韻体のロマンス William of Palerne 『パレルヌのウィリアム』には
魔術と死霊術に精通している継母も登場する。
But lelliche þat ladi in ӡouþe hadde lerned miche schame,
(But loyally that lady in yours had learned much scheme,
貴方の女性は多くの策略を学んでいた。)
for al þe werk of wicchecraft wel ynouӡ che couӡþe;
(for all the work of witchcraft well not she posses knowledge;
魔法のすべての技量に対して彼女は知識を持っていない。
)
nede nadde ӡhe namore of nigramauncy to lere
(it was necessary not had she nomore necromancy to learn(teach)
彼女はもう黒魔術、降霊術(occult art) を学ぶ(教える)必要はなかったのだ。)
(William of Palerne An Alliterative Romance ed.G.H.V.Bunt,
Mediaevalia Groningana 6) (Groningen,1985),II. 117-19)
彼女は継嗣のスペインの王子を狼男に変身させる。
自分の子供を後継ぎにしたいからだ。
The Saven Sages D版:
3405
That [scho] let the treson make
(That she let the treason meke
彼女は謀反を起させた。)
主語代名詞の非表現例
[scho] she を補う。
3408-3415
和訳は第15物語参照
彼女は答えた。「閣下、皇帝陛下/
神の慈愛と陛下の名誉のために。/
王の望みがなされるように判定を下されよ。/
陛下が心に決めたことに私は従うまでです。/
断じて私は告発を否定することはできないけれども/
私にもたらされた世間のわるいうわさ。/
陛下の王子が陳述した事柄は/
確かに事実です。」/
3416-3417
Hyt was altogydir my red,
(It was completely my plot
それは完全に私の筋書きだ。)
For I wolde he hadde ben dede."
(For I would he had been dead.
私は彼を亡き者にしようと欲したのです。)
他のバージョンでは
皇后は言い訳をする。彼女は王子が自分或い皇帝を殺して
帝国を乗っ取るのではないかと恐れた。
彼女は先妻でなく彼女自身が生んだ子供を相続人にしたかったのだ。
3418-20
和訳は第15物語参照
このように反逆罪を犯した皇后は/
邪悪の念を認めました。/
サタンの誘惑に駆られて妖術を用いたことを。/
3421-3
And anoon scho was schent,
(And immediately she was ruined
その権謀術数は失敗に終わり直ちに彼女は身を滅ぼすはめになりました。)
And bounden swyth fast,
(And bound very fast, そして急速に身柄を拘束した。 )
And hadde hire juggement at the last.
(And at last judgement had been passed on her.
遂に彼女に審判が下されたのでした。 )
その他のバージョンでは
皇后は炎炎と燃え立つ焚火の真中に投げ込まれて焼死したと
詳しく書かれている。
3424
和訳は第15物語参照:
王子の命は守られ/
3425
And the Emperesse lees hire lyf.
(And the Empress lost her life.
皇后は命を落としました。)
[....この後数行欠.....写本に空白無しだが........
............]
詩行が欠けているために突然
皇帝の状況を理解する対象(主題)としてシフトしたのである。
3426-54
七賢人達は皇帝の息子を正しい方法で支えました。/
昼の間も夜の間も/
そして学者達二人と五人/
彼らは王子を助けて命を救いました。/
七編の物語を彼らが語ることによって/
七人の師達は大変豪胆でしたから/
策略をめぐらした反逆者に対して語りました。/
王子の継母である皇后の物語に相反して。/
したがって皇帝は/
彼らを大変尊重して待遇し/
彼が考えたことすべてを/
七賢人達の助言によって彼が遂行しました。/
それから一生男やもめ暮らしをして/
彼は再び妻を持とうとはしませんでした。/
それは片時も忘れなかったからです。/
彼女が謀反を起した理由も。/
もはや彼は彼女の事件を強いて扱うことはしませんでした。/
彼らがそれ以上のいざこざを巻き起こさないように。/
彼は幸福な生活を送り始め/
純潔な男になりました。/
そして彼自身が精一杯(全身全霊)で努力しました。/
法律によって王民を統治するために/
また陽気に生き幸福な状態で/
神が思し召した時に死んで/
heuen-riche 天国に行きました。/
天の喜びと幸いは永遠です。/
神が同じ至福を私達にお与え下さる事を
お祈りしましょう。/
大地を踏みしめたものは誰でも(万人)/
アーメン、アーメン、 チャリティーの為に。/
七賢物語詩の終わりはそれぞれの版で微妙に異なるが
一般的に結末は定型的なものである。
D版はnigrimancye(
妖術、降霊術,黒魔術、
オカルト)を用いたと自白した皇后(
彼女自身は降霊術師でも魔女でもない)を処刑して以来
妻を持たない男としての皇帝のその後の人生を語っている点が
ユニークである。
E版も注目に値する。
(皇帝の死で結末をつけたD版には書いてない王子が即位し"Jesus, that ys kyng of heuyn,...
Jesu, for hys modyr loue, Amen...(イエス,それは天国の王...イエス、母の愛のためにアーメン で大団円となる。)
父の死後王子は大修道院を建て
父の霊魂をなぐさめしずめる歌
を歌い書物を読むために
7人の学者たちを修道士に雇う。
E版:その箇所3448-3555までの和訳例:
そしてその子供は長い年月を過ごした。/
常に真実を愛し悪を憎んだ。/
生涯を名誉にあずかり/
彼は父の皇帝を守り続けた。/
父親が死んだ時/
貴重な場所を作らせた。/
そして荘厳な修道院を開設し、/
七人の学者がそこに連れて来られた。/
E版 3556-59
And euyr more to rede and synge
(And every occasion more to read and sing
あらゆる機会に読み歌う)
For his fadyr, withowte lesynge,
(For his father's soul, without remedy or release or deliver
父の霊魂のために、(多様な直訳誤訳例?)救済措置のない、or 救いの手を差し伸べられない、
降伏することなく、手放すことなく、誘惑、危機から救われない、諦めずに、etc.etc.)
And tho was the chylde made Emperor
(And then was the child made Emperor
そしてその時その子は皇帝になった。)
And kept hys londe with grete honoure
(And kept his land with great honor.
そして彼の国を大切に守り通した。)
D版
3453
That euer in erth ӡed schodde.
(Who ever trod the earth
大地を踏みしめた者、or 大地を踏んだことのある者、万人)
Dr.Thomas Wright(1810-1877)編集版の
写本のこの箇所は
That never in erth ӡed schodde
しかし
never
は
ever
の誤写に相違ない。
この行の意味は
who ever trod (went,walked) the earth :
(地球、or 大地 を歩いた者 or 踏んだ者)
(すなわち全人類)
中期英語辞書:
ӡed は、went (go の過去形)
trod は、(tread の 過去形)
写本を誤写したneverだと
who never trod (went) the earth:
(地球、大地.地面を歩かなかった、踏まなかった者)
それ故
Dr.Jill Whitelock 編集(2005年版)において
never は [ever] に校訂された。
★D版写字生の筆写エラーというのが最後の訳注である。
最終行:
3453行
Amen, amen, ffor charité
の 2重子音字 ffor の ff も for の f に校訂されているが
それは本文の注解noteに記載がない。
注現代英語解釈
who□ever trod the earth は
whoever ではいけないのかについて。
who□never だと
whonever の語彙は辞書にない。
whonever trod , went the earth
とスペースを間違えて打ち込むと
DeepL 機械翻訳は
『大地を踏みしめた、歩いた誰であろうと』
と訳す。
参考
中期英語 ӡed は
現代英語 tread の過去形 trod について
● ジーニアス英和辞典
tread 例文
1.Stop treading mud all over my clean kitchen floor!
きれいなキッチンの床を泥だらけにしないで
2.tread the boards [おどけて]舞台に立つ[で演じる]
3.Fools rush in where angels fear to tread.
(ことわざ)天使が恐れて進みかねている場所に愚者は突っ込むものだ。
《行動を起こす前によく考えよという意味》
4.walk(tread) (on) a tightrope 綱渡りをする;危ないことをする、
5.tread on his foot (誤って)彼の足を踏む(会話ではstepの方がふつう)
6.tread on one's inferiors 部下を踏み台にしてのしあがる
7.Sorry--did I tread on your foot? すみません、足を踏みませんでしたか
8.tread through the grass 芝地を歩いていく、
9.tread cautiously [carefully, lightly] 慎重にふるまう,
10.tread grapes to make wine ワインを作るためにブドウを踏みつける
11.tread (out)the juice from grapes ブドウを踏んでジュースを搾る,
12.tread the streets 通りを歩く
13.tread the path of virtue 有徳の道を歩く、善に生きる。
14.hear his loud tread on the stairs 階段に彼のやかましい足音が聞こえる
15.walk with a heavy [cautious] tread ドシドシ[そっと]歩く
16.walk with (a) velvet tread 静かに歩く
Dr. Jill Whitelock,
ジル・ホワイトロック博士の編集した本
The Seven Sages of Rome Midland Version
ローマ七賢物語 ミッドランドバージョン一冊翻訳終わり。
所感:翻訳によって学ばせていただいたのは
現存する中世期の英語写本9種類(D,C,R,F,A,Ar,E,B,As)に関して
その共通、異本要素を研究すればするほど
あるイギリス中世の中期英語本を(Middle English parent version)数多の写字生達が共通種本としていたとならざるをえない。
それは現存せずその未発見本は、古フランス語散文バージョン
(Old French prose Version A※)から派生したという
分枝系図へのジル・ホワイト博士が呈した疑問でした。
その一種である
D版 ミッドランドバージョンの写本は、Dr.Thomas Wright (1810-1877)によって校訂されたのですが
2005年にDr.Jill Whitelock がさらに校訂し編集した本のintroduction は本文の注釈と共に
革新的です。
原文には原典がありそのオリジナルが現存していない以上もう研究の余地はないという行き止まりの
"The Seven Sages"について
現存しない共通種本を完全な韻律詩と仮定することによって
現存D版(D版を写本したD写字生は一人ではなく複数いたとみなす。)に書いてある文字は
中世期に生きていた人々が読み書きしていた中期英語の語彙と語形、綴り字であり歴史の流れのなかでそれを読み解いてゆくことができるのです。
その解読には他の中期英語バージョンと古フランスバージョンとの比較も不可欠となります。
D版は物語の写本の読み方が素晴らしく特異であると褒めたたえる一方でミッドランドバージョンの韻律が規則正しくない箇所については
D版写字生にとって未知の(unfamiliar)語形だったからである。そこは馴染めない土地だったとして
ミッドランドバージョンD版を写本したのはNorthern:北部地方出身者となり
また脚韻以外でも筆写ミスがあると批判し校訂するのです。
また不可解な部分について他の中期英語版も古フランス語バージョンA※も
D版に手がかりを一切与えていないという書き方をしているNote(注解)もあります。
お国ならではの所蔵品(ケンブリッジ大学図書館)に対して文字を書き換えたり補足したりできた現代のThe Seven Sages Roma 研究の権威者が提言している事が愉快でもあり博士のミッドランドバージョンを完訳できました。
卒論ローマ七賢物語 サウサーンバージョン (SOUTHERN VERSION)と比較